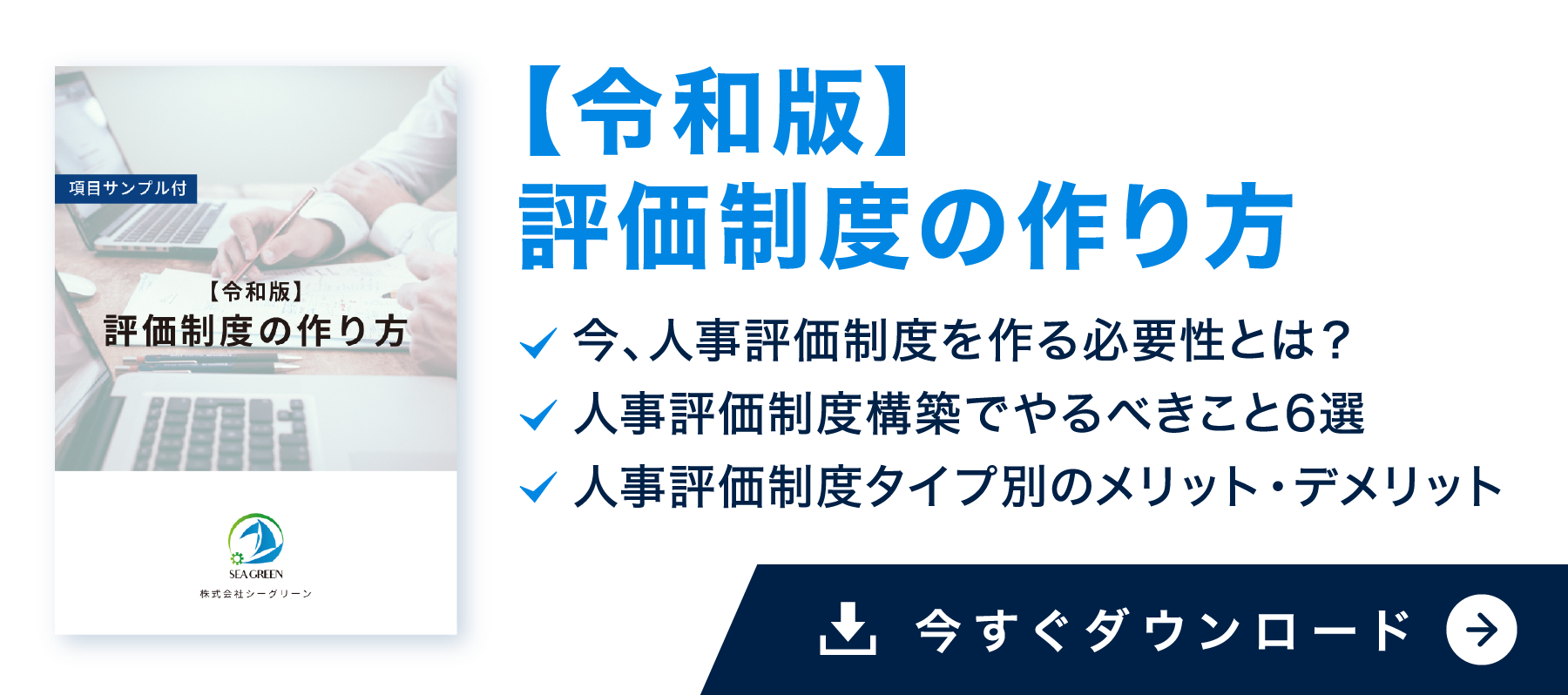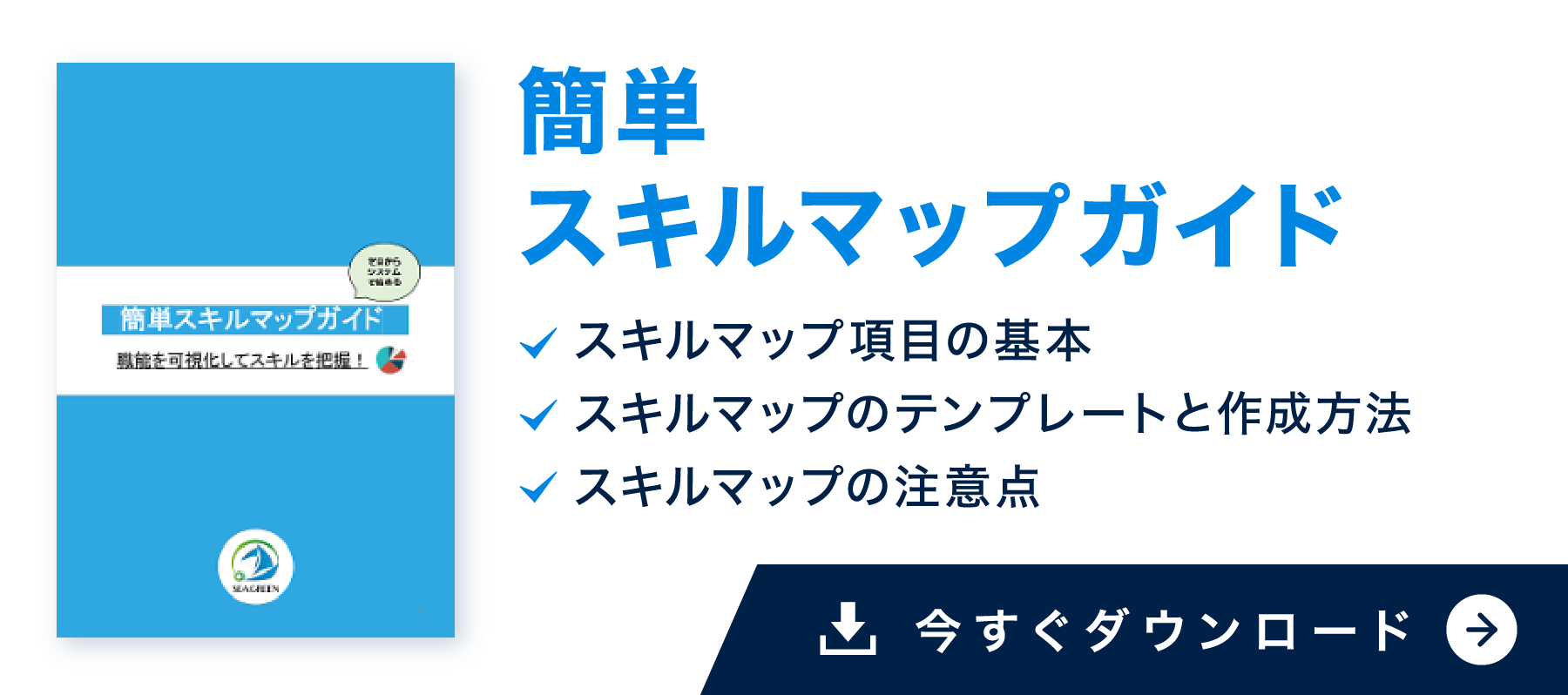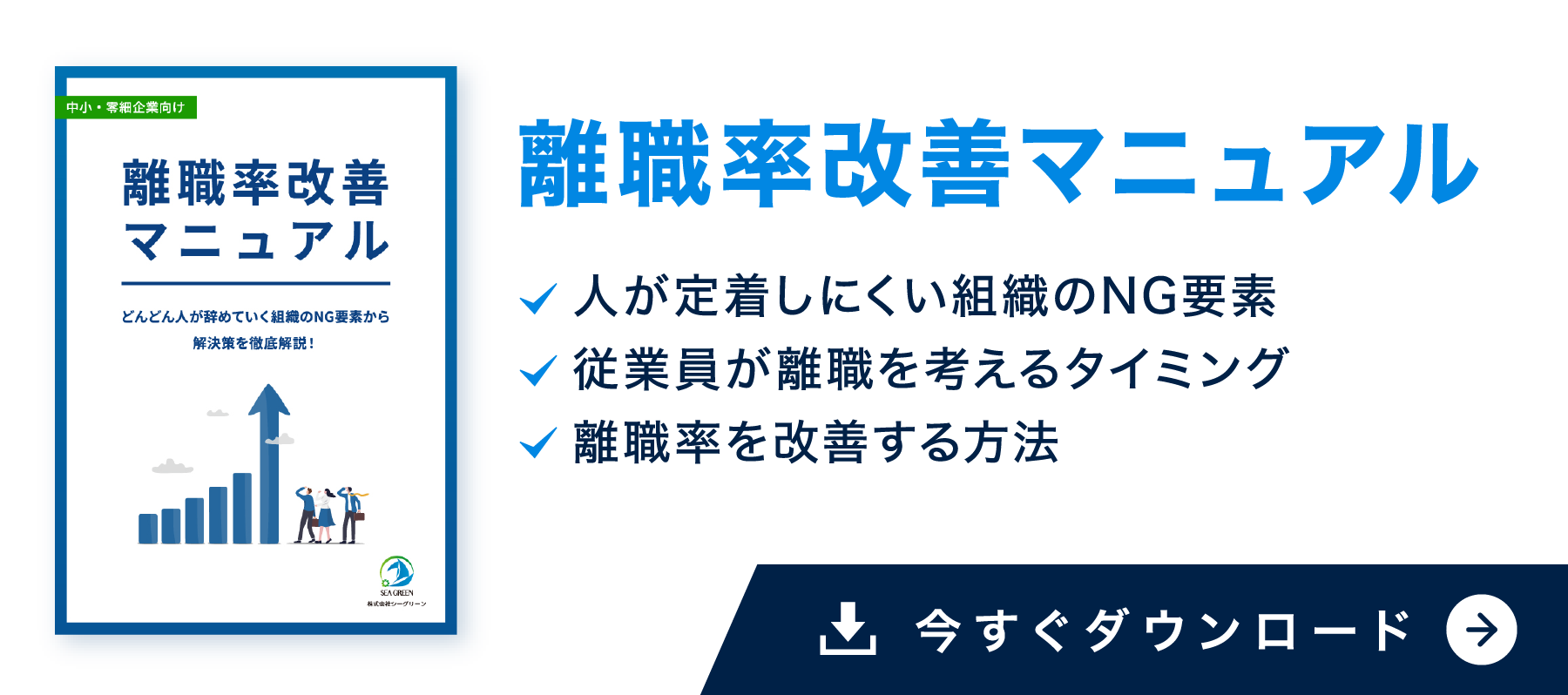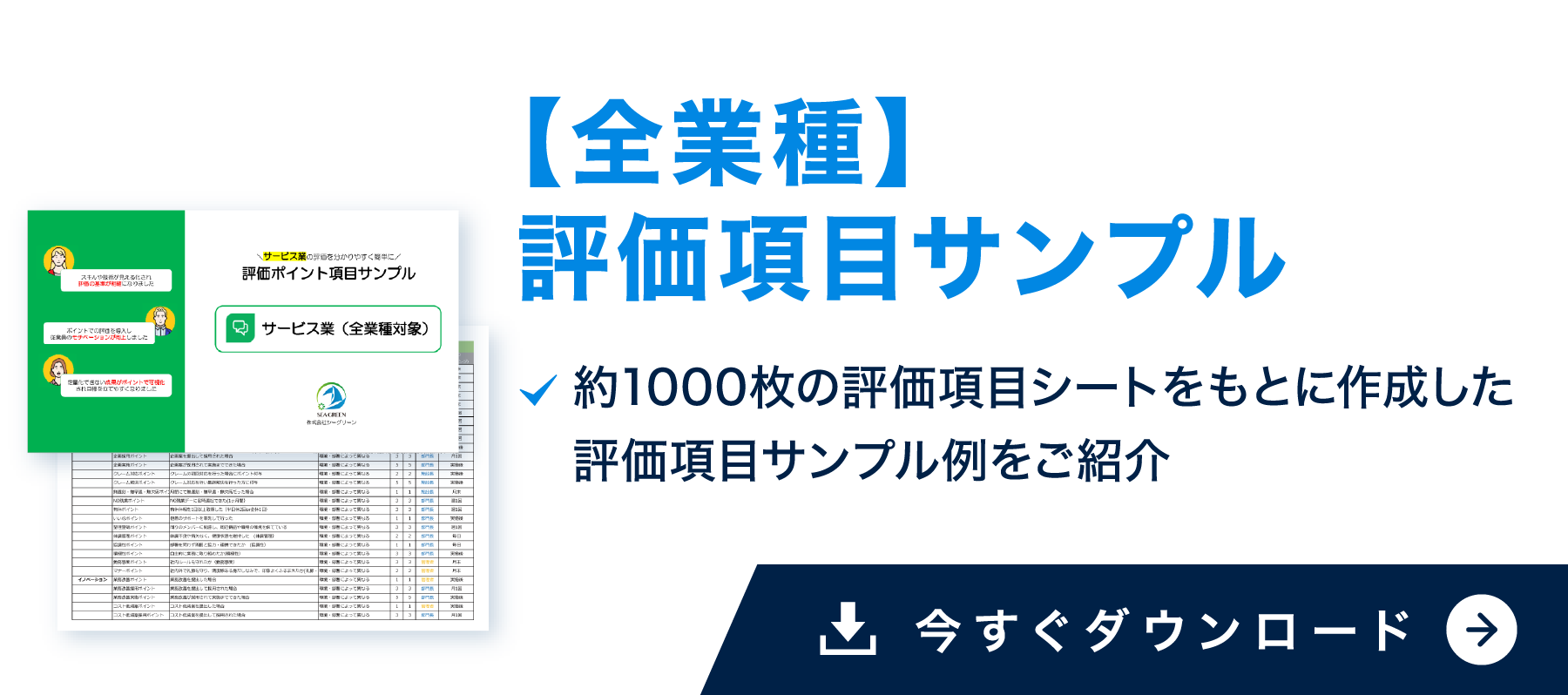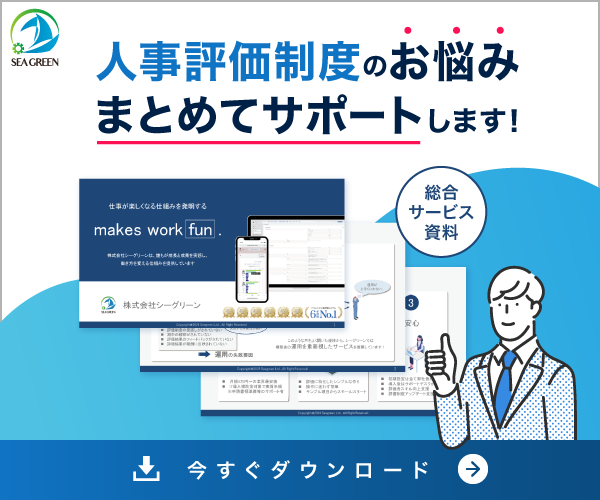人事評価制度と給与について、双方を連動すべきかと、悩む事例は多く見受けられます。実際のところ、人事評価制度と給与は連動させる方がよいのでしょうか?
そこで当記事では、人事評価制度と給与を「連動すべきか否か」と「その理由」について解説します。双方を連携させる際の手順や注意点も取り上げるため、経営者や人事総務を担当する方はぜひ参考にしてください。
目次
【結論】人事評価制度と給与は連動させるとよい

結論から述べると、「人事評価制度」と「給与」は連動させることが望ましいといえます。
そもそも人事評価制度とは、従業員の頑張りを適切に評価するための仕組みです。また給与とは、従業員の労働に対して支払う対価であり、企業への貢献度に準じて金額も変化する流れが一般的です。
日々の頑張りを対価に反映することで、従業員は「自分の努力を正当に判断してもらえた」と思うでしょう。従業員の努力を可視化させる意味でも、人事評価制度と給与の連動を推奨します。
人事評価制度と給与を連動させるメリット
人事評価制度と給与は、頑張りを「給与金額」という目に見える形で示せるという背景から、連動する流れがよいとわかりました。ここでは、人事評価制度と給与を連動させることで、企業が得られるメリットを解説します。
モチベーションアップによる生産性向上

人事評価の結果が高く、給与金額も評価結果に準じた内容であれば、従業員のモチベーションアップが期待できます。モチベーションが高まれば、作業効率も上がり、通常業務の処理速度がはやくなることも多いでしょう。主体的な気持ちも芽生えやすく、プラスアルファの行動や新たなアイデアの創出なども期待できます。
通常業務の速度がはやまり、主体的な行動も実践できると、個人はもちろんのことチーム全体の生産性もアップする傾向にあります。企業全体における生産性の向上は、業績アップにもつながるでしょう。
定着率が高まる
頑張りを給与金額に反映させることで、日々の業務に尽力し精一杯取り組めば、結果につながる点を明示できます。「どういった基準で給与査定を実施するか」についてもオープンにすれば、主観ではなく客観的に決めていることも示せるため、企業への信頼も増す傾向にあります。
信頼できる企業には、帰属意識も芽生えやすく、「この会社で長く働きたい」や「企業の売上や発展に貢献したい」といった気持ちを生じさせやすいでしょう。結果として、定着率アップも期待できます。
人材獲得に役立つ
評価と給与を連動させ、「従業員の頑張りを適切に反映する」点を社外にアピールすれば、人材獲得に役立つでしょう。企業が自ら公表せずとも、現役の従業員や元従業員から、口コミとして周囲に広がることも考えられます。
少子高齢化による慢性的な人材不足で、多くの企業が以前よりも人材獲得に苦戦していることも事実です。求職者優位な昨今において、人事評価制度と給与の適切な連動は、人材獲得に役立つ大きなポイントとなり得るでしょう。
人事評価制度と給与を連動させるデメリット
人事評価制度と給与を連動させると、多くのメリットがあるとわかりました。一方で、双方を連動させることでデメリットが生じる可能性もあります。
人事評価制度と給与の連動による主なデメリットは、以下の通りです。
業績が悪くても、頑張った人に多くの給与を支払う

人事評価制度と給与を連動させると、当然ながら、高評価の人は給与金額が高くなる傾向にあります。言い換えれば、たとえ企業の業績が思わしくなくても、頑張った人には相応の給与を支給する必要があります。
とはいえ、業績が悪いときに「給与の還元を控える仕組み」にすると、高評価を得る優秀な従業員が辞める可能性もあるでしょう。そのため、業績が上がらなかった時期も踏まえ、高評価者に多くの給与を支払っても経営が傾かないようにバランスを取ることが重要です。
整備に手間がかかる
人事評価制度と給与を連動させる際には、ベースとなる人事評価制度はもちろんのこと、給与制度の整備も不可欠です。人事評価制度と給与制度の整備後も、双方の連携作業が必要になります。適切な人事評価制度と給与制度を連携させた後には、運用ルールの制定・改定や、従業員への周知もかかせません。
一連の作業には「専門的な知識」も要するため、企業担当者のスキルが不足するケースも見受けられます。スキル不足の状態ですすめることは難しいことから、担当者のスキルアップを試みる必要もあるでしょう。
人事評価制度と給与の連動における注意点・ポイント
人事評価制度と給与を連動させるには、ポイントを押さえた対応が求められます。
ここでは、人事評価制度と給与の連動における注意点・ポイントについて解説します。
評価基準を適切に設定する

評価基準とは、企業目標を達成するために、各従業員が何をどれだけ達成できればよいかを示したものです。人事評価制度の精度を左右する「評価基準」にズレが生じると、企業に貢献した人の評価が低くなり、貢献していない人の評価が高くなるといった事態にもなりかねません。そのため、評価基準を適切に設定することは必須事項です。
適切な評価基準から成り立つ人事評価制度は、企業目標の達成に貢献した従業員に対し、高評価を導きます。適切な人事評価制度を給与と連動させれば、貢献度の高い人に対し、相応の給与を支払う流れにつながります。
業績が悪い時期も考慮する
会社自体の業績が上がっていれば、頑張っている従業員に対し、問題なく高い給与を支給できるでしょう。しかし物事には波があるため、業績がふるわない時期もあるのが実情です。人事評価制度と給与を連動させている場合には、たとえ会社の業績が悪くても、頑張っている従業員には相応の給与を支給する必要があります。
そのため、企業の業績が悪いケースも踏まえ、制度を設計することが不可欠です。また、業績が思わしくないときの対応を検討する際には、従業員のモチベーションを下げさせない点も考慮することが大切です。
人事評価制度と給与の連動を公表する
人事評価制度と給与を連動させたら、よほど特別な事情がないかぎり、内容を従業員に公表することをおすすめします。また、単に「人事評価制度と給与制度が連動している」と伝えるだけでなく、以下のような内容も伝えることが大切です。
- 人事評価制度の評価基準
- 評価結果をどれほどの割合で給与に反映しているか
- 給与金額が変更になるタイミング(例:半年ごとの変更)
企業から詳細な内容を聞くことで、制度に対する納得感につながります。また企業への安心感・信頼アップも期待できるでしょう。
評価は「絶対評価」で、報酬は「相対反映」を意識する
評価結果は、あくまで本人の頑張りを判断することから、ほかメンバーの評価結果とは無関係な「絶対評価」が基本です。一方で報酬に反映する原資には限りがあるため、報酬を「相対的な判断」で捉えることは当然でしょう。
人事評価制度と給与を連動させる場合には、絶対評価の評価結果と相対反映する報酬を組み合わせて考えます。従業員が10名存在し、極端な話「全員が最高評価」であれば、報酬原資を10等分するといった流れです。
人事評価制度と給与を連動する手順
人事評価制度と給与を連動する際には、以下のステップにそってすすめるとスムーズです。
1、等級を定める
まずは、人事評価制度や処遇の核となる「等級」を定めます。等級とは、ランクのことであり、数個の段階に分別し、職位や必要とする能力を決めています。
~等級の例~
- 1級:一般社員A…与えられた業務を適切に実行する
- 2級:一般社員B…与えられた業務に加え、自身で課題を見つけられる
- 3級:主任…一般社員のマネジメントができる
- 4級…課長…主任に対してマネジメント指導ができる
- 5級…部長…企業経営に向けた提案・実行ができる
2、評価基準を定める
つづいて、人事評価制度の内容を左右するといっても過言ではない「評価基準」を設定します。評価基準を定める際には、企業目標の達成を念頭におき、どういった内容にすれば目標達成に近づくかを踏まえることが大切です。先述で定めたそれぞれの「等級」に対し、個別に評価基準を設定します。
~評価基準の例~
- S…基準を完全にこえた状態
- A…基準に到達した
- B…従業員の今までの実力をこえたものの、基準には到達していない
- C…基準に到達していない
- D…基準にまったくおよばない
3、給与テーブルを整備する
給与金額を決定するための「給与テーブル」を整備します。給与テーブルも従業員に公表することで、給与金額の透明性を維持できるでしょう。給与テーブルは、主に以下の3種類に分類できます。
- 1、段階号俸表…多くの企業で採択。評価が常に累積される。
- 2、複数賃率表…以前の評価を累積せず、「現段階」の評価で判断する
- 3、賃金ゾーン表…等級に応じて一定の幅があり、同一賃金の考え方に合う。
企業の目標や特徴に応じて、給与テーブルの種類を選ぶことが大切です。
4、等級・評価基準・給与テーブルを連携させる
先述の流れに即し、「等級」「評価基準」「給与テーブル」を定めたら、テストとして、実際にどういった金額が導かれるかを検証します。一度従業員に公表した制度を変更することは容易でないため、テストの段階で不具合や齟齬がないかを入念にチェックしましょう。
また「等級」「評価基準」「給与テーブル」ともに、専門性が問われる分野であるため、自社内での完結が難しいケースも往々にして見受けられます。
あらかじめ、すべての内容を外部に依頼するケースも多いでしょう。
人事評価制度と給与を適切に連携させ、企業の成長につなげよう
人事評価制度と給与を適切に連携させると、従業員は目に見えて「自身の頑張り」がわかるため、モチベーションアップにつながります。各自の意欲が高まり、生産効率がアップすれば、企業の成長にも直結します。
人事評価制度と給与を適切に連携させるには、ベースとなる人事評価制度の精度を高めることが重要です。人事評価制度の精度を高め、スムーズに給与と連携させるには、株式会社シーグリーンの人事評価システム「ヒョーカクラウド」がおすすめです。
給与計算でkintonを活用している場合、「ヒョーカクラウド」と容易に連携できます。
また、人事評価制度の見直しや構築から依頼・相談したい場合には、人事評価システムもパッケージ内に含まれた「人事評価構築パッケージ」がおすすめです。人事評価制度と給与を適切に連携させ、企業の成長につなげたい場合には、「ヒョーカクラウド」「人事評価構築パッケージ」をぜひご検討ください。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル