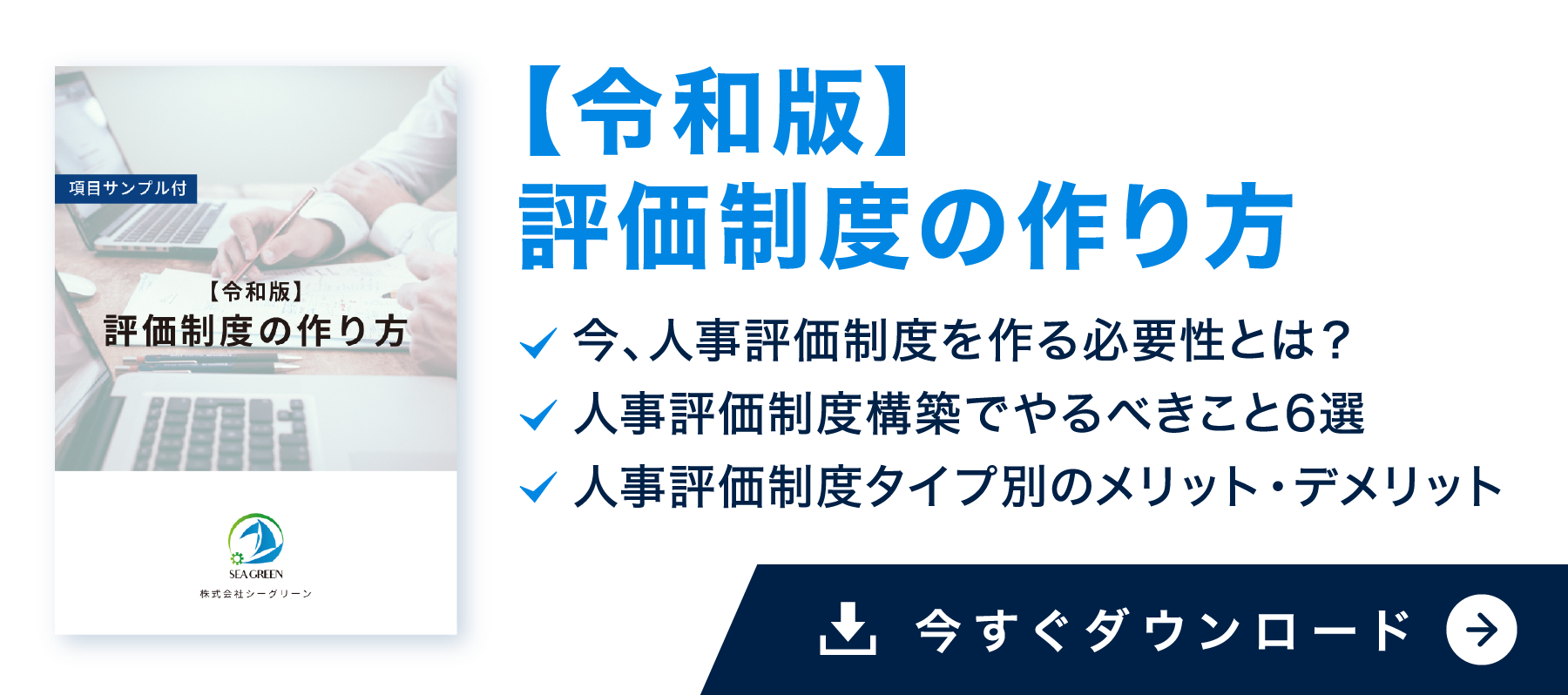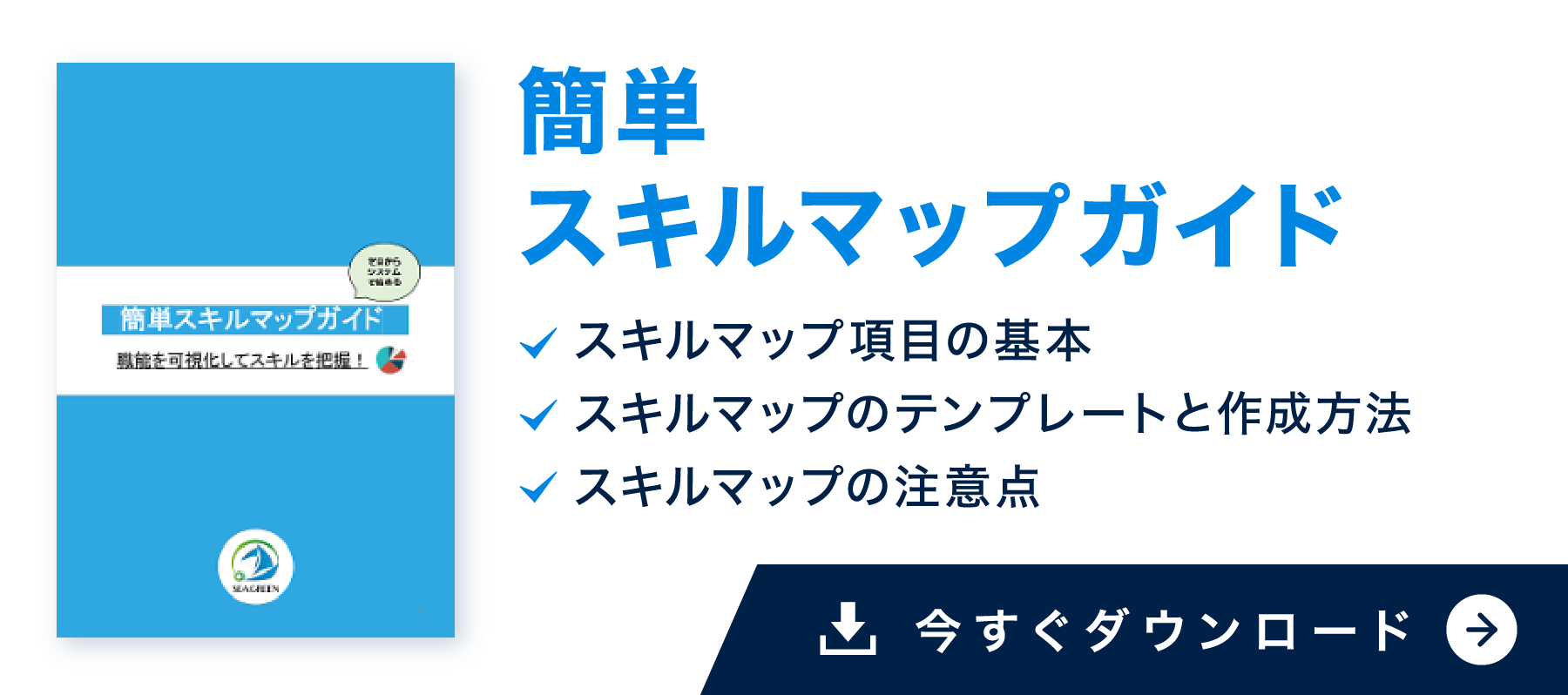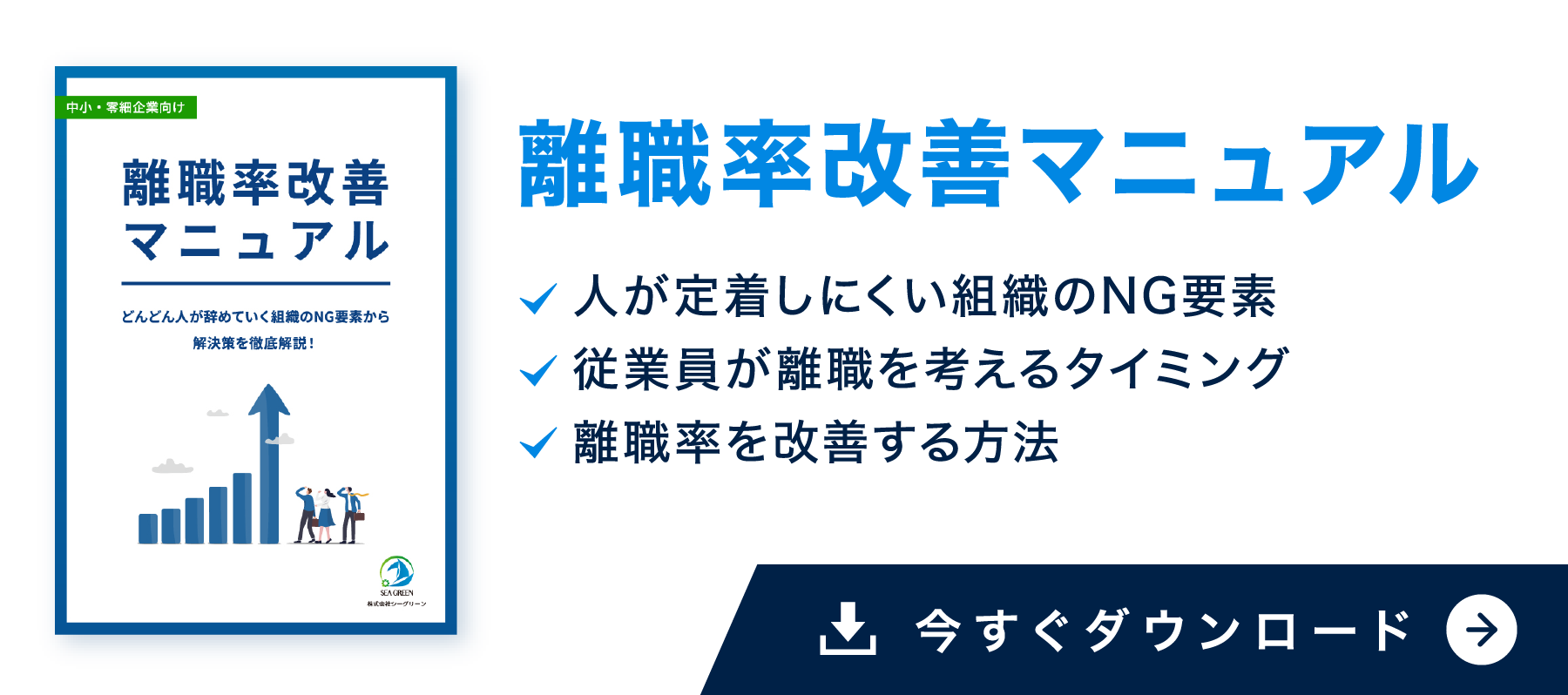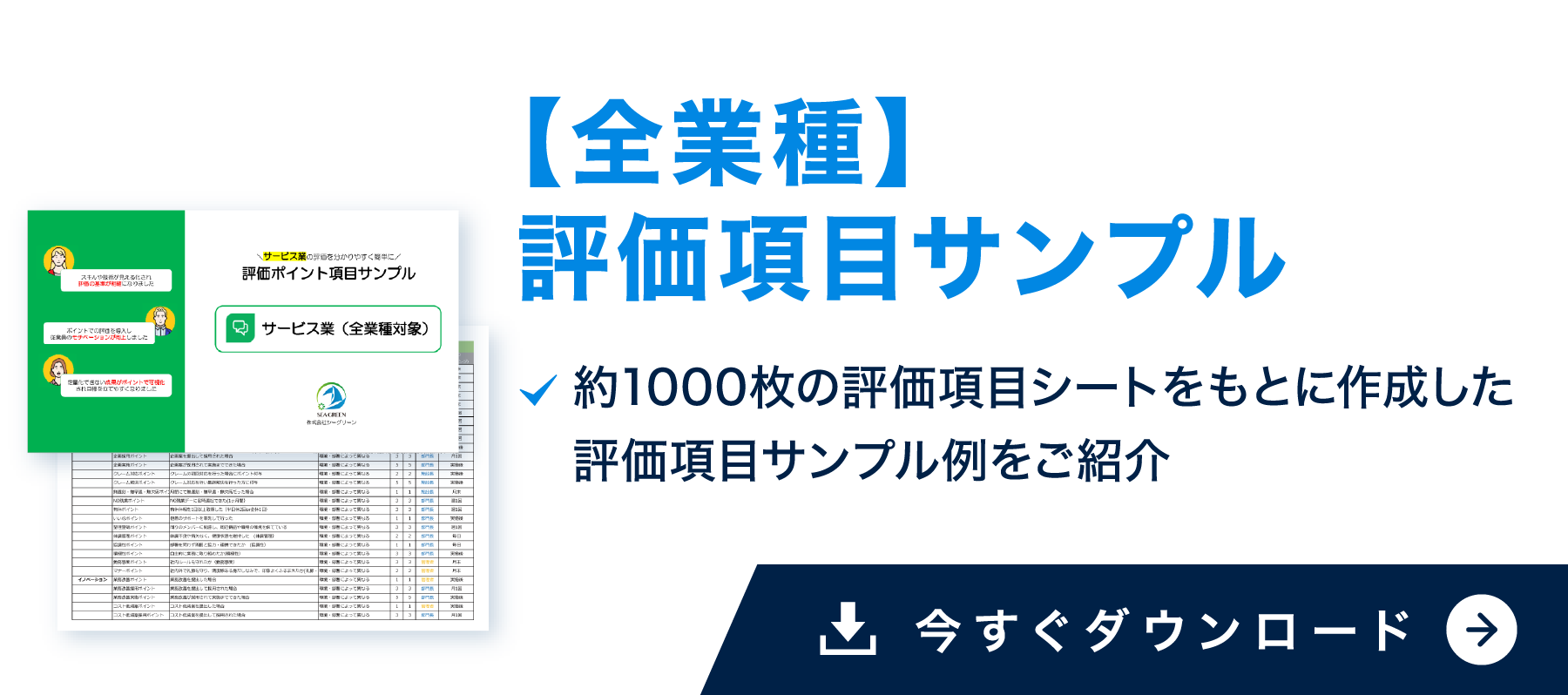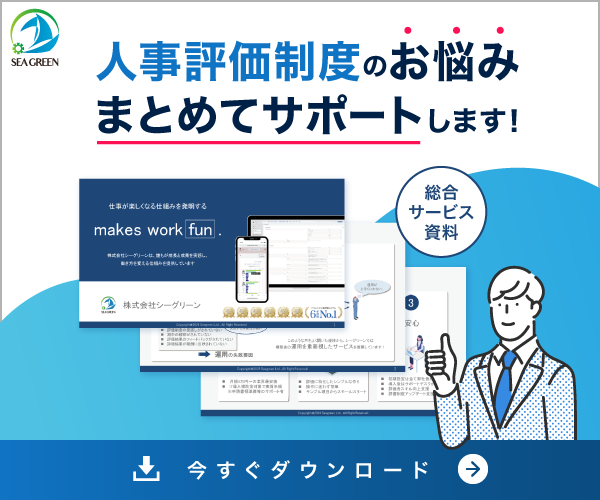従業員の頑張りを反映しようと給与アップを試みても、「従業員のモチベーションが上がらない」と悩むケースも多く見受けられます。給与査定の方法を改善しても、効果がなければ徒労に終わる可能性があるでしょう。
そこで当記事では、効果がある給与査定を目指すべく、従業員のやる気アップにつながる「給与制度の運用手順」や「コツ」について解説します。適切な給与制度を用意したい場合には、ぜひ参考にしてください。
目次
多くの従業員が給与査定で不満に思うこと
せっかく給与制度を設けても、内容によっては、従業員の不満が募ることもあるでしょう。ここでは、多くの従業員が「給与査定で不満に思うこと」について解説します。
頑張りに見合った金額ではない

自分の頑張りに対し、提示された給与金額が「見合った内容ではない」と思うと、不満が生じる傾向にあります。不満の背景には、頑張りに対し「自分が重視する点」と「企業が重視する点」が異なるといった事実が隠れていることも多いでしょう。
双方のギャップが埋まらない限り、従業員は「頑張っているのに給与に反映してくれない」と思いつづけます。一方で企業は「貢献度の低い従業員だ」と考え、お互いの溝が深まると予想されます。
利益重視の視点で評価されている
営業部のトップセールスなど、「わかりやすく会社の売上に貢献している人」だけが高い給与を支給されている場合、従業員から「利益重視の視点で評価している」と思われる可能性があるでしょう。
会社の利益は、特定の人物が生み出しているとは限らず、バックオフィスや技術者など、多様なポジションの人が協力してこそ獲得できるものです。利益重視の視点でのみ評価をしていれば、優秀な事務職や技術者のモチベーションを低下させる可能性が高まります。
基準が不明確で公平感に欠ける
給与金額が、どういった理由・手順で導かれたかが不明であれば、従業員が不満をもつのは当然だといえます。基準が不明確であれば、「上司の好き嫌いで判断している」や「経営者の一存で決めている」と思われる傾向にあり、不公平感を増長させるでしょう。
同期入社のメンバーや後輩が自分よりも高い給与金額であった場合には、企業から「金額の差」について納得できる内容を示してもらわなければ、会社への不満は募る一方です。
モチベーション低下だけではない!不適切な給与査定の影響
不適切な給与査定は、モチベーション低下だけを招くわけではありません。ほかにも、以下のようなデメリットを生じさせます。
モチベーション低下による生産性ダウン

「不適切な給与査定」だと思い、モチベーションが低下すれば、日々の業務を積極的に行えなくなるものです。前向きな気持ちで仕事に取り組めない場合には、作業効率も下がる傾向にあります。また、ミスも生じやすくなります。
会社はチーム単位で仕事を行うことから、1人の「作業効率の低下」は、チーム全体の生産性ダウンにつながるでしょう。生産性が低下すると、品質の維持やサービスの提供が難しくなる傾向にあります。
離職者の増加
給与査定への不満からモチベーションダウンが続くと、「適切に評価してもらえる会社で働きたい」などと考え、離職の決断に至る可能性が高まります。同じような状況の人が増えれば、離職者が相次ぐといった事態も想定できるでしょう。
離職者が増加すると、周囲の社員に対する負担が増えることも必須です。給与査定への不満がなかった社員であっても、業務負担の増加によるストレスなどから、「会社を辞めたい」という気持ちが生じる可能性も否定できません。
人材獲得が難しくなる恐れ
多くの従業員にとって、給与査定の内容が納得できないものであれば、一部の従業員から「給与査定が不適切な会社だ」という噂を外部に流される可能性があります。昨今では情報がインターネット上やSNSでスピーディーに拡散されることも多く、「給与査定が不適切だ」といった情報が発信されれば、あっという間に情報が広がるケースも少なくありません。
マイナス情報が広がれば、人材獲得が難しくなる恐れもあるでしょう。ただでさえ、少子高齢化で人材獲得が難航する時代において、マイナスな内容が外部に流れる事態は避けたいものです。
従業員のやる気を高める給与査定のコツ・注意点
従業員のやる気を高めるには、適切な給与査定を実施することが大切です。適切な給与査定を行うコツ・注意点は、以下の通りです。
ベースとなる人事評価制度の整備が必須

給与制度は、人事評価制度とリンクさせることが望ましく、ベースとなる人事評価制度の整備は必須です。
人事評価制度自体が存在しない場合には、制度の新設が求められます。人事評価制度が存在しても、設置から数年が経過する場合には、企業の現状に即さない可能性もあるため、内容を見直すことが大切です。
また「人事評価システム」と「給与制度」が連携するサービスを使えば、スムーズな給与査定を実施できるでしょう。給与計算でkintoneを使用している場合、人事評価システム「ヒョーカクラウド/評価ポイント」を活用すれば、双方を簡単に連携できます。
給与査定で期待する効果が現れているかをチェックする
給与査定でモチベーションアップを期待するなら、効果の度合いを、随時チェックする必要があります。モチベーションが上がっていなければ、給与査定の見直しが必要です。
従業員のモチベーション状況を調べるには、「1on1」や「パルスサーベイ」がおすすめです。
1on1を行うことで、従業員の本音を引き出しやすくなります。また匿名でのパルスサーベイを実施すれば、1on1でも聞けなかったような心の声を確認できる可能性もあるでしょう。パルスサーベイの結果を比較・分析すれば、給与査定や人事評価制度における課題も見えやすくなります。
給与査定の基準を明確化し公表する
適切な給与査定を実現するにあたり、査定基準の明確化は欠かせません。基準が存在することで、誰が給与査定を実施しても、同一かつ公平な結果を導けるでしょう。
また明確化した基準は、企業担当者だけにとどめるのではなく、すべての従業員に公表することが大切です。基準を公開すれば、「どういった部分を頑張れば給与額が高くなるか」がわかるため、給与査定に対する納得度を高められるでしょう。
給与額が低かった場合にも、基準をチェックすれば、「〇〇の部分が不足していたから、査定結果が低かった」と理解しやすくなります。
給与査定の基本的な運用手順
給与査定は、どのように行われるのでしょうか?ここでは、給与査定の「基本的な運用手順」について解説します。
1、基本給のルールを定める


基本給とは、給与の「毎回必ずもらえる一定金額」に該当する部分です。基本給には、各種手当(例:通勤手当・資格手当)や残業代は含まれません。
一般的に給与額を改定する際には、基本給を変更することから、あらかじめ基本給に対するルールを定めておく必要があります。基本給のルールを制定する際には、「企業の業績によって」どのように変化させるかを条件に定めるとよいでしょう。業績に対する変化を条件に定めれば、利益が上がれば基本給が上がり、利益が下がれば基本給も下がることから、公平性を保てます。
2、仕事給のルールを定める
仕事給とは、給与の「業務内容や各自の役目によって変動する」部分に該当します。また仕事給に、社歴や年齢は反映されません。
ルールに関しては、業務内容や階級に応じて、どのように昇給・降給するかを金額ベースで定めるとよいでしょう。 降給した人の気持ちを踏まえ、半年に1度ペースで改定することも大切です。1年に一度の改定速度だと、降給した人はモチベーションが下がったままで長い期間を過ごすことになります。「半年後には昇給できるかもしれない」と希望をもってもらう意味でも、改定のタイミングは半年ペースがおすすめです。
3、調整給のルールを定める
調整給(調整手当)とは、給与の「会社が独自に支給する部分」に該当します。調整給という字でわかる通り、給与を調整し、バランスを取る役目があります。たとえば、基本給と仕事給を合算したものの、トータル金額が少なすぎる場合に、調整給を加えるといった流れです。
また調整給は「やむを得ない場合」に加える要素であることから、最終的には調整給を0円にする流れが望ましいでしょう。調整給が発生した際に、「どのように調整給を減らすか」や「調整給が発生する期間」について定めておくことも重要です。
4、1~3のルールをまとめ、従業員に周知する
基本給・仕事給・調整給のルールを定めたら、すべての内容を従業員に周知することが大切です。「成果で給与額が変化する」と頭でわかっていても、全容が見えなければ、不審に思う気持ちが出てくるのも当然だといえます。
あらかじめ給与査定に関する「すべてのルール」を公開すれば、給与額の根拠がわかるため、たとえ給与額が下がっても納得しやすくなります。
またルールの公開によって、給与査定に関する透明性を示せることから、企業に対する信頼を低下させにくいでしょう。
5、実際に運用し、効果測定を繰り返す
基本給・仕事給・調整給のルールを定めても、実際に運用した結果、思い通りに進むとは限りません。何事も、トライアンドエラーが大切です。
「運用→課題発見→改善策を実施→分析」という流れで効果測定を繰り返すことで、より自社に即した給与査定ルールを設けられるでしょう。
効果測定を繰り返すなかで、1on1などで現場の声も取り入れれば、経営陣からは見えなかったリアルな本音も見えやすくなります。
適切な給与査定を実施し、従業員のやる気を高めよう
適切な給与査定を実施し、従業員のやる気を高めるには、人事評価制度の整備・給与査定ルールの整備が不可欠です。しかし「人事評価制度」「給与査定」ともに、専門的な知識を要する内容であるため、自社内での対応が難しい場合にはプロへの依頼が確実かつおすすめだといえます。
株式会社シーグリーンの人事評価構築パッケージは、人事評価制度の構築から運用までトータル的にサポートする「人事評価システムつき」のパッケージです。kintoneとの連携によって、人事評価制度と報酬制度も簡単に連動できます。
適切な「人事評価制度」と「給与査定のルール」を整備し、従業員のやる気につなげたいと考える場合には、人事評価構築パッケージをご検討ください。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル