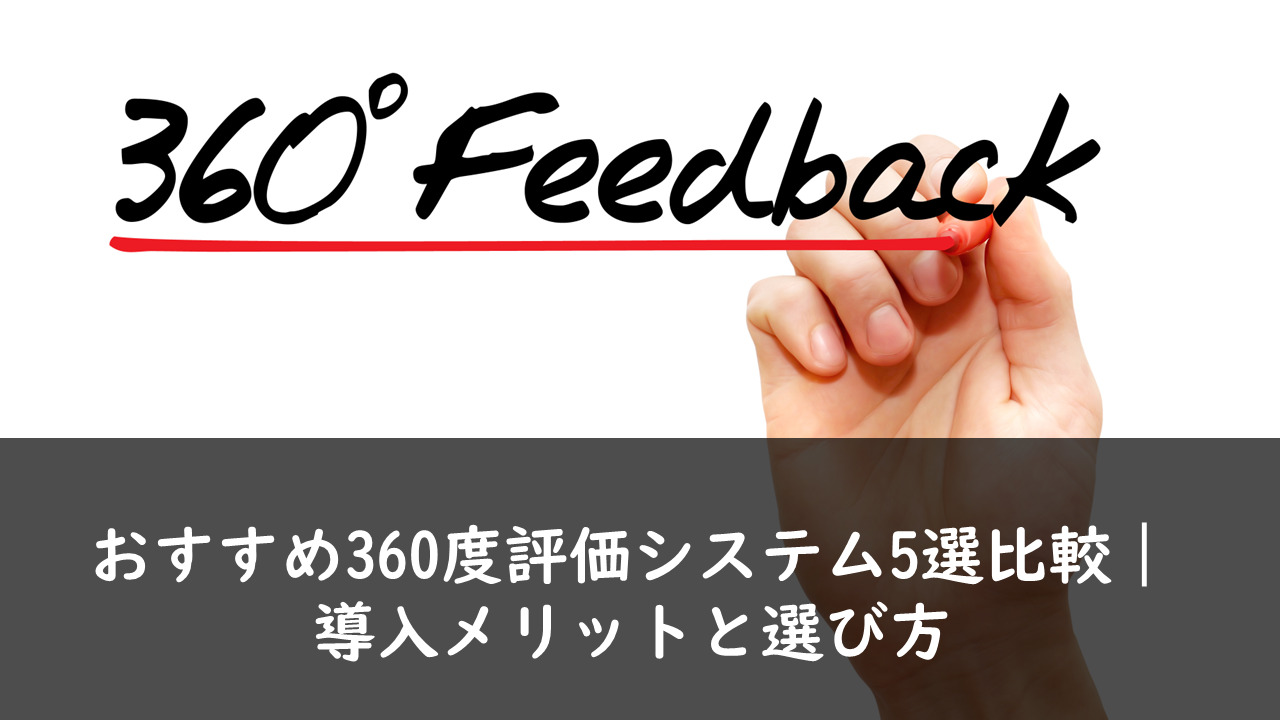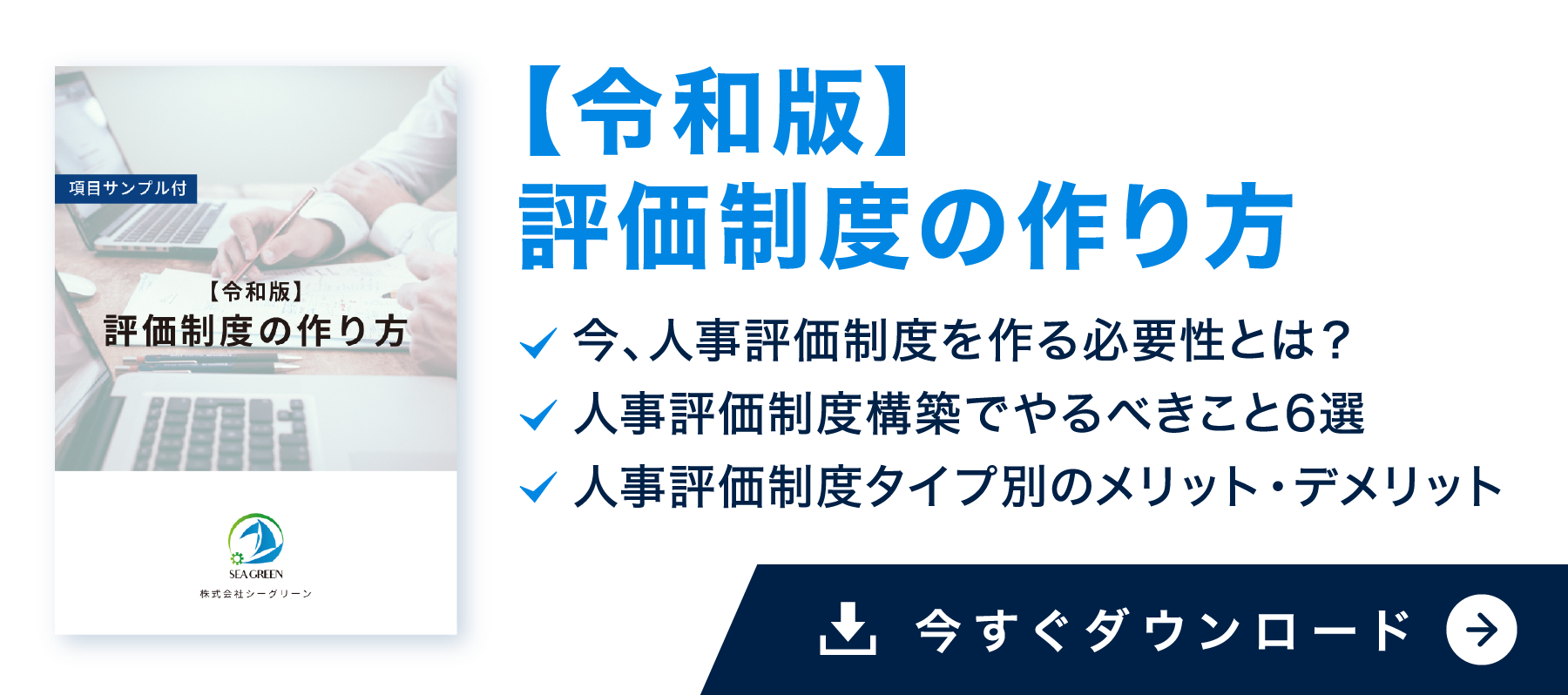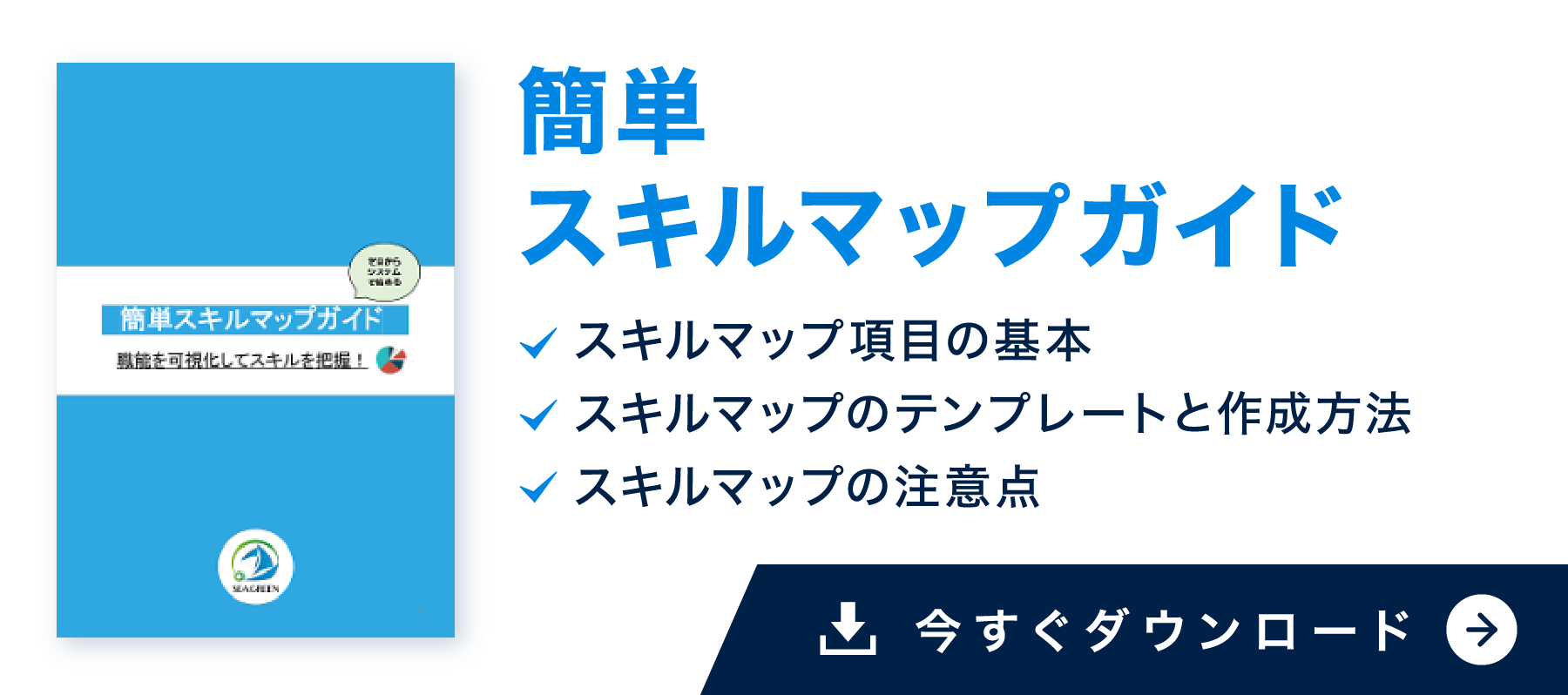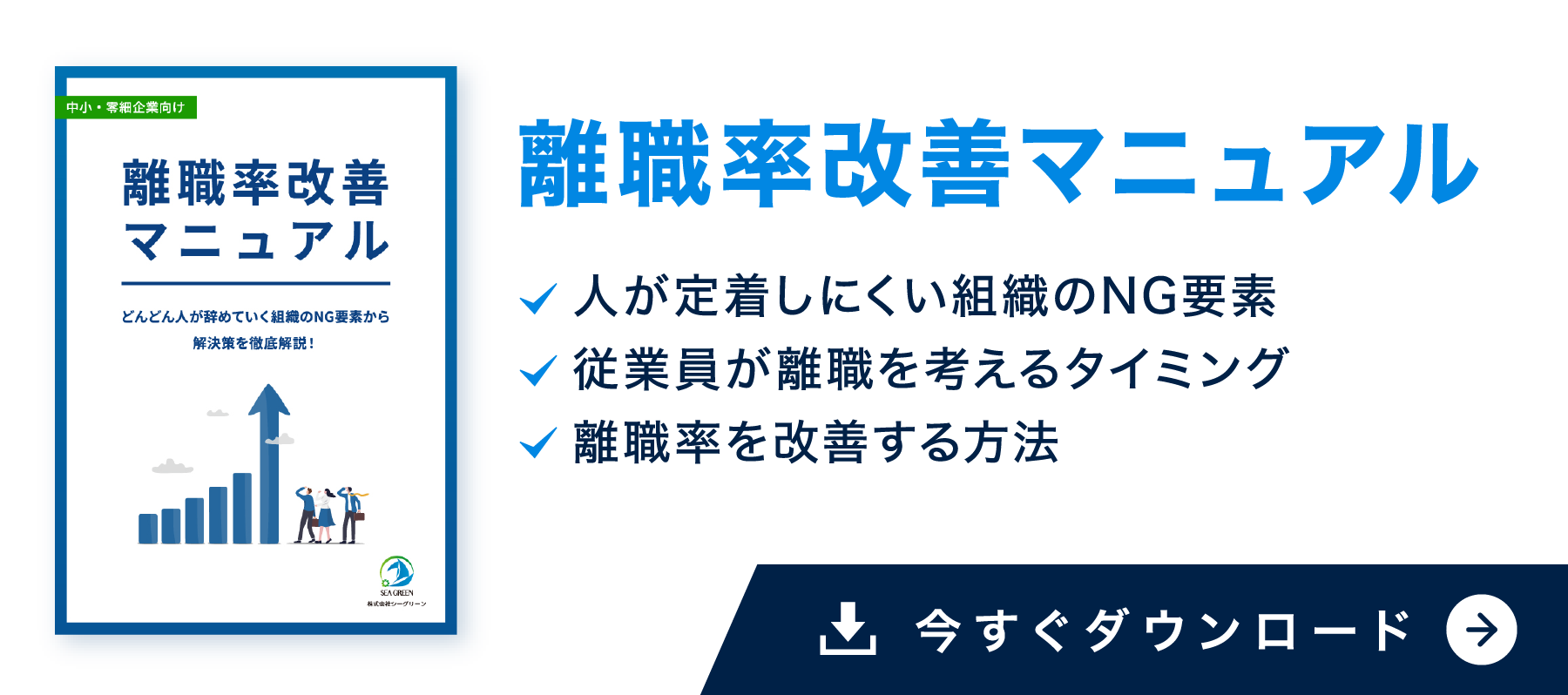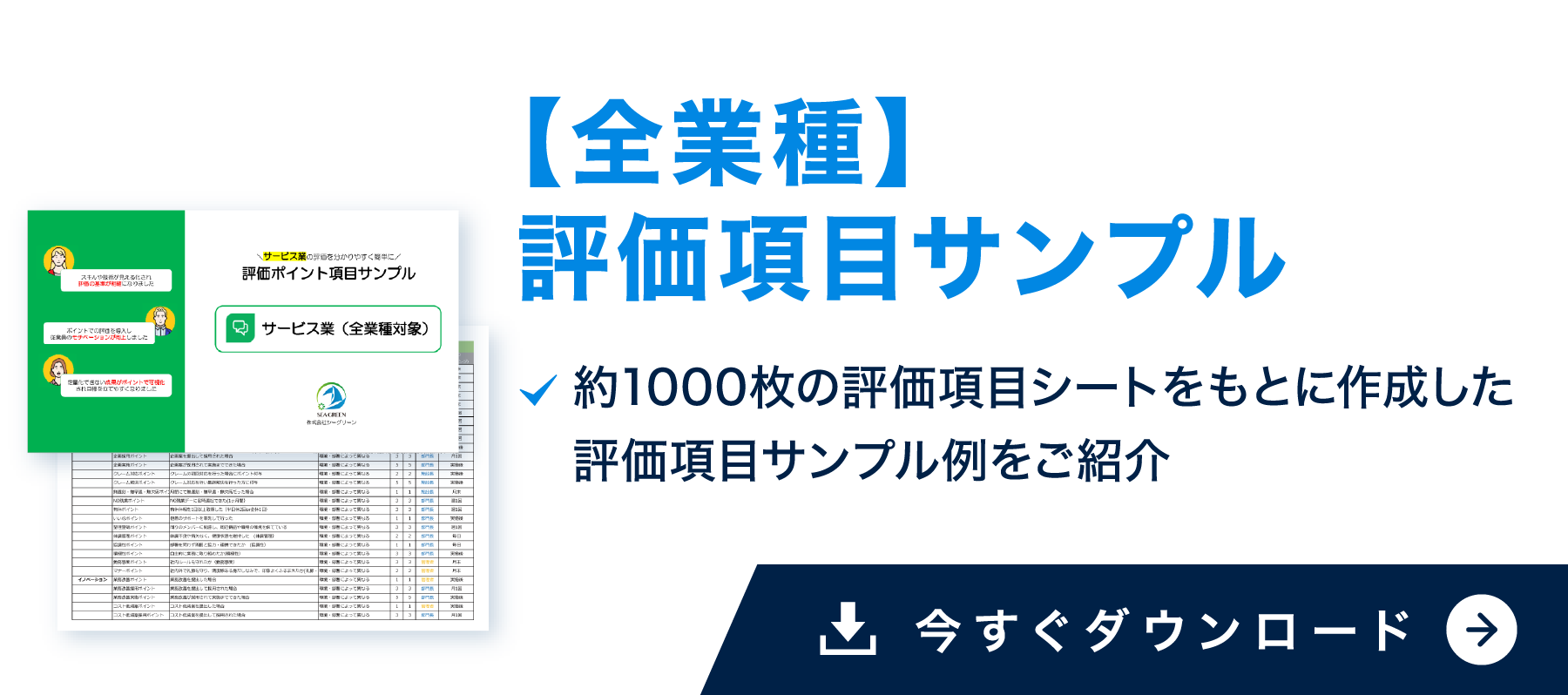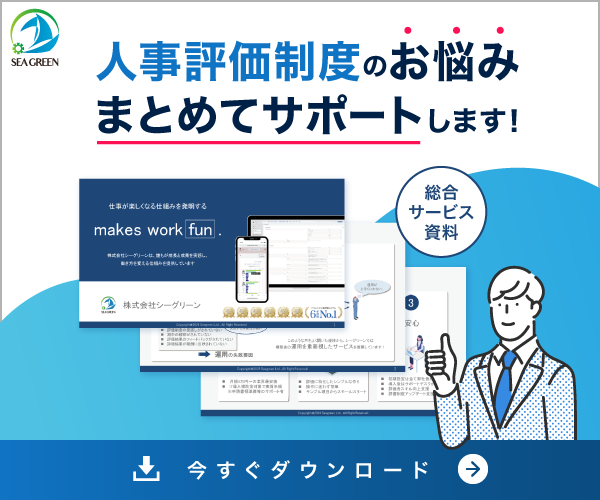360度評価システムを導入すると、評価プロセスが可視化・効率化されるため、主観に偏らない客観的な評価を実現できます。公平さを維持でき、納得度の高いフィードバックも可能になります。しかし、「どのようにシステムを選べばよいか」といった疑問や、「具体的なサービスを比較したい」といった悩みも生じるものです。
そこで当記事では、おすすめの360度評価システム5選を比較紹介すると同時に、導入するメリットや選び方についても解説します。360度評価システム選びを成功させたい場合には、ぜひ当記事をお役立てください。
目次
360度評価システムとは
そもそも360度評価システムとは、どういったものなのでしょうか。ここでは、「360度評価を行う目的」や「システム化の必要性」といった側面から、押さえておくとよい概要について解説します。
360度評価の目的とは

360度評価の主な目的は、「公平で多角的な人材評価をする」と、「自己認識と他者評価のギャップを把握する」の2点です。経営者や上司のみによる評価では、評価者の好き嫌いや価値観が反映しやすく、評価の公平性を維持しにくい問題があります。
360度評価は、上司・同僚・部下といった複数の関係者が評価するので、特定の意見で評価をするわけではありません。そのため、客観的かつ公平な評価を実現しやすいことが特徴です。
また、評価結果をフィードバックすれば、「自己認識」と「他者からの評価」についてギャップを把握できます。ギャップを小さくする努力をすれば、自己成長にもつながります。360度評価について、さらに詳しい内容を知りたい場合には、以下の記事もチェックしてみてください。
360度評価とは?成功事例から学ぶ効果的なやり方と重要性を解説
360度評価システムの必要性
360度評価の効果を最大化するには、専用システムの導入が不可欠です。360度評価についてExcelなどでアナログ運用する場合、評価依頼・回収・集計・レポート作成など、多くの手間がかかる傾向にあります。評価者が多いほど作業負担は増大することから、その分においてミスも発生しがちです。
専用システムを導入すれば、評価依頼の自動送信・リマインド・データの集計、レポート作成などを自動化できるため、人事担当者の負担軽減につながります。評価者が多い場合にも、システム内に沿って評価すればよいため、ミスも最小限に抑えられるでしょう。
システム化すれば、匿名性の確保やデータ分析機能など、Excelでは難しい高度な機能も利用できます。
360度評価システム導入のメリット
360度評価システムを導入すると、多くのメリットを享受できます。主なメリットは、以下の通りです。
評価業務を効率化できる

Excel管理のようなアナログな方法で360度評価を実施する場合、設問項目の作成から配布、回収や集計に至るまで、多くの作業を人が行う必要がありました。評価する対象者が増えると、手間も増えるため、入力ミスなどの発生確率も高まります。
360度評価システムを導入すれば、煩雑な評価業務の効率化が可能となり、ヒューマンエラーも減らすことが可能です。その理由として、搭載された「評価テンプレート」によって、設問作成にかかる時間を削減できることが挙げられます。また、評価依頼やリマインドも自動化できるため、進捗管理の負担を軽減できます。回収したデータも自動的に集計されるため、迅速な収集が可能です。
評価の客観性と透明性の向上
360度評価は、複数の関係者が評価するため、主観に偏らない客観的な評価が期待できます。しかし、誰が評価したのかが分かってしまうと、気まずさから本音を書きづらく、表面的な意見に留まる人も少なくありません。たとえば、メールでの提出や投票箱への提出といったアナログな方法では、匿名にしたつもりでも、文面や筆跡などで評価者が特定されがちです。
360度評価システムならば、筆跡といった物理的な手がかりはもちろん、誰がどの意見を述べたのかも評価対象者には分からないようシステム上で管理されます。複数視点からの「リアルな意見」も集めやすくなり、客観性が担保されやすくなるでしょう。評価される側の納得感も向上しやすくなります。
データ活用による人材育成を促進できる
360度評価システムには、複数の評価者による各社員への評価データが集約されます。評価項目ごとの点数や具体的なコメントが蓄積され、システムが自動集計および分析を行います。すると、各社員の強み(=高評価の項目)と弱み(=低評価の項目や改善コメントが多い項目)が明確になります。強みや弱みについて、数値やグラフで視覚的に可視化することも可能です。
可視化されたデータは、育成計画の客観的な根拠となるでしょう。たとえば、課題が明確になった社員に対して、システムで目標設定テンプレートを提示したり、具体的な育成アクションを計画できます。また、強みを伸ばす施策や、強みを活かせる役割への配置も検討可能になるでしょう。
360度評価システム導入のデメリット
360度評価システムには、多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。システム導入を検討する際には、デメリットも把握したうえで選ぶことが大切です。主なデメリットは、以下の通りです。
運用負担が増える可能性がある

360度評価システムを導入すると、システム運用者に対し、負担が増える可能性があります。たとえば初期には、「評価項目の設計」「運用ルールの策定」「評価者への操作説明」といった業務が発生します。評価項目が多岐にわたる場合や、評価対象者が広範囲の場合には、より多くの時間を要するでしょう。また、評価者からの問い合わせ対応や、評価の進捗管理なども発生します。
しかし運用負担は、適切なシステム選定によって、減らすことが可能です。たとえば、自社の評価目的に合致したテンプレート搭載のシステムを選定、サポート体制が充実したベンダーを選ぶなどです。また一部の部署から段階的に導入すれば、現場の混乱を避けられるため、運用負担の軽減やスムーズな導入につながります。
コストがかかる
360度評価システムの導入には、初期費用や月額利用料といったコストが発生します。またシステムによっては、サポート費用やオプション料などが発生することもあるでしょう。
しかしコストは、単なる支出ではなく、将来への投資ともいえます。360度評価システムの導入は、煩雑だった評価業務を効率化し、人事担当者の時間と労力削減につながります。また、客観的で納得性の高い評価は、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体の生産性向上に貢献する可能性もあるでしょう。そのため、短期的な導入コストだけでなく、中・長期的な視点から費用対効果を見極めることが重要です。
適切なシステム選定と運用によって、初期投資を上回るリターンが期待できる可能性も高いでしょう。
360度評価システムを選ぶ際のチェックポイント
360度評価システム選びを成功させたい場合には、ポイントを踏まえて選ぶことが大切です。ここでは、システム選びでチェックしたいポイントについて解説します。
課題解決につながるかどうか

360度評価システムを選ぶ際には、システム導入によって、自社が抱える課題を解決できるかをチェックしましょう。最新機能が搭載されている、コストが安いといった理由だけで選ぶと、導入後に「結局、何も解決されなかった」という事態になりかねません。
たとえば、「主観的な評価による偏りが大きい」という課題を抱えているのであれば、複数名からの客観的な意見を取り入れられるシステムが必要です。また、「従業員の成長機会が不足している」のであれば、具体的なフィードバックによって、改善を促せる機能があるとよいでしょう。
ほかにも「部署間のコミュニケーション不足が課題」であれば、評価を通じて互いを理解し、連携を促進するシステムが有効かもしれません。
操作性・使いやすさ
360度評価システムを使うのは、評価する人と評価される従業員です。また、評価する人・評価される人ともに、ITスキルにばらつきがあるのも当然です。そのため、導入する360度システムには、誰もがストレスなく利用できるシンプルな設計が求められます。直観的に操作ができ、評価フローがスムーズにできることが理想です。
操作が複雑で分かりにくいシステムは、評価の質を低下させるだけでなく、評価する人・評価される人の作業負担を増やしてしまいます。また、最終的にはシステム活用が形骸化する恐れもあるでしょう。そのため、無料トライアルなどを積極的に活用し、操作性や使いやすさを確かめることが重要です。
サポート体制
どのようなシステムを導入しても、操作や利用方法に関する疑問は避けられません。とくに導入初期は、その傾向が顕著です。自社にITに詳しい人材がいても、システム独自の操作や設定については不明点が生じうるため、手厚いサポートは不可欠です。導入時はもちろんのこと、長期的な活用も支援してもらえるかを確認しましょう。
また、初めて360度評価を導入する企業では、「何から始めればよいか」「自社に合った評価項目は何か」など、疑問が多く生じる可能性があります。そのため、評価項目の設計や制度構築に関するコンサルティングを受けられるかどうかもポイントです。ベンダーのサポート体制をしっかりと見極めることが、スムーズな導入と継続的なシステム活用につながります。
コストパフォーマンス
360度評価システムを選ぶ際に、価格だけで判断することはおすすめできません。初期費用・月額・年額料金といった金額面だけで考えるのではなく、「提供される機能」「サポートの質」「システムの使いやすさ」などを総合的に検討し、価格に見合う価値があるかを判断することです。つまり、導入によって評価業務がどれだけ効率化されるか、従業員の成長や組織全体のパフォーマンス向上にどれほど貢献できるかといった効果を考慮します。
無料トライアルを利用して操作感を試したり、導入企業の事例を参考にすることも、コストパフォーマンスを見極めるうえで役立つでしょう。
別の評価方法にも対応できる
360度評価は、単独で運用しても有効な評価手法だといえます。しかし、MBOやコンピテンシー評価といった別の評価方法と組み合わせることで、より精緻な人事評価が可能になるケースも多く見受けられます。また、現在は「360度評価のみでよい」と考えていても、組織の成長や戦略の変化に伴い、将来的に別の評価方法を導入する可能性もあるでしょう。
そのため、360度評価システムを選ぶ際には、将来的な評価制度の変更に対応できるかどうかも重要なポイントです。システム選定をする際には、「API連携による別のシステムとの連携」や「初期から複数の評価方法に対応できる仕様であるか」も確認しましょう。
おすすめの360度評価システム5選
ここでは、おすすめの360度評価システムについて、具体的な5つのサービスを紹介します。システムを選ぶ際に、ぜひ参考にしてください。それぞれのサービスの詳細は、以下の通りです。
評価ポイント

『評価ポイント』は、社員の頑張りをリアルタイムで評価し、社員のモチベーションアップとアクティビティを見える化できる人事評価システムです。従来の360度評価に加え、ピアボーナス機能も搭載しています。
ピアボーナスでは、日々の業務や対応に対し、従業員同士で「いいねポイント」を付与できます。日常的な評価と360度評価を組み合わせることで、よりタイムリーで詳細なフィードバックが可能に。貯めたポイントは、福利厚生として活用できるため、エンゲージメント向上にもつながります。
導入実績は、300社以上。導入から運用まで、丁寧にサポートする手厚い体制も特徴です。個人の行動ログや日報の作成・共有機能も備わっており、チーム内の連携強化にも貢献します。
【機能】
- 360°評価に加え、ピアボーナスも(従業員同士で気軽に感謝を伝えられる)
- 獲得ポイントを福利厚生として活用可
- 個人の行動ログを記録
- 日報の作成・共有
【料金】
- 初期費用:0円
- 月額料金:要問い合わせ
HRBrain 360°評価

『HRBRain 360度評価』は、360°評価の実施と分析に特化した、クラウド型システムです。複数の視点を取り入れた評価プロセスについて、効率的な運用が期待できます。評価項目の設定から評価者への依頼・回答の回収・集計・分析まで、360度評価に関わる一連の業務をスムーズに行えます。
オプション機能として、業績評価や目標管理の機能も利用可能なため、360度評価の結果と合わせて、総合的な人材評価・管理を実現できるでしょう。
【機能】
- 360度評価に特化
- 業績評価や目標管理も実施可(オプション)
- 人材データの統合分析
- 各種テンプレート
【料金】
- 初期費用:0円
- 月額料金:人数に応じて変化
タレントパレット

タレントパレットは、AIを活用した人材データ分析に強みを持つ、大企業向けのタレントマネジメントシステムです。多岐にわたる人材データを集約し、AIがデータ解析することで、組織の課題発見や戦略的な人材配置、育成計画の策定などを支援。
多様な評価に対応しており、360度評価の機能も搭載しています。人事に必要な機能を、ワンストップで提供することも特徴です。
【機能】
- 360度評価・MBO・コンピテンシーなどの評価機能
- アンケート
- 異動シミュレーション
【料金】
- 初期費用:あり
- 月額料金:社員数に応じて変化
CBASE360°

CBASE360°は、360度評価に特化したクラウド型システムです。360°評価の運用からフィードバックまで、一連のプロセスを実施できます。単にシステムを提供するだけではなく、360度評価の効果を最大限に引き出すべく、研修プログラムを提供することも徳陽です。360°評価に特化したシンプルな設計であるため、まずは360度評価だけを導入したい企業に適するでしょう。
【機能】
- 360°評価に特化
- 各種テンプレート
- レポート作成
【料金】
- 人数に準ずるため、要見積もり
リアルワン

リアルワンは、人事コンサルティング会社が提供する、360度評価に特化したサービスです。360度評価の導入における企画・設計から、評価に必要な調査票の作成、実施・分析まで包括的に対応します。
コンサルティング会社ならではの知見を活かしつつ、企業文化や課題に合わせた評価項目や評価方法を提案してもらえるでしょう。
【機能】
- 360°評価に特化
- 自動レポート
- アンケート
- スキルアップ動画(見放題)
【料金】
- 人数に準ずるため、要見積もり
360度評価システムを導入するまでの基本ステップ
360度評価システムを導入するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。システム導入までの基本的なステップは、以下の通りです。
STEP1: 自社の導入目的を明確にする

システムを選ぶ際には、指針となる軸が必要になります。軸となるのは、「なぜ自社は360度評価システムを導入するか」という目的意識です。人材育成が目的か、適正な配置に活用したいのかなど、目的によって選ぶべきシステムは異なります。
自社の導入目的を明確にするには、経営層や人事担当者だけでなく、現場のマネージャーや従業員の意見もヒアリングすることが大切です。関係者の意見を集めることで、現状の評価制度に対する課題や、360度評価に期待する効果が見えてくるでしょう。意見を整理した後には、「人材育成」「評価の公平性向上」「コミュニケーション促進」など、具体的なキーワードで目的を特定します。特定した目的の中で、優先度の高い内容を絞り込み、最終的な導入目標として言語化します。
STEP2: 予算と運用体制を確認する
次に、システム導入にかけられる費用と、運用を担当する人員体制を決めましょう。また、予算内で導入可能なシステムであっても、自社の評価目的を達成できる機能が備わっていなければ意味がありません。コストパフォーマンスを検討する際には、初期費用や月額利用料だけでなく、カスタマイズ費やオプションなどの追加料金も含めて比較することが重要です。
また、システム運用を担当できる人員をどの程度確保できるかや、運用担当者のITスキルや人事評価に関する知識レベルも考慮します。初めて360度評価を導入する企業では、制度設計やシステム操作に関するノウハウの蓄積に時間がかかるため、手厚いサポート体制のサービスを選ぶと安心です。
STEP3: 必要な機能を洗い出す
導入目的を達成するために、どのような機能が360度評価システムに求められるかを洗い出します。評価項目の作成・評価の実施・データの集計や分析・評価結果のフィードバックといった各ステップにおいて、必要な機能をリストアップしましょう。
例として、「評価項目をカスタマイズできるか」「評価の進捗状況をリアルタイムで確認できるか」「フィードバックを効率的に行えるか」などが挙げられます。目標達成を実現できるような機能が搭載されているシステムが、候補となるでしょう。候補となったシステムは、次のステップで比較検討していきます。
STEP4: 複数のシステムを比較検討する
複数の360度評価システムを選べたら、比較検討を行いましょう。その際に、デモ版の提供や無料トライアルの実施を行っている場合、積極的な活用をおすすめします。実際に使ってみることで、操作性や使いやすさを評価できるでしょう。評価担当者だけでなく、管理職や一般社員にも触ってもらい、意見を聞くことも参考になります。誰でも容易に操作できるシステムは、導入後の定着率に寄与し、スムーズな運用にもつながるでしょう。直感的な操作性は、評価者の負担を軽減し、回答率の向上にもつながります。
また、サポート体制の充実度やセキュリティ対策なども、比較のポイントとなります。ほかにも、導入実績やユーザーからの口コミ評価も参考になるでしょう。
360度評価システム導入でよくある失敗パターン
360度評価システムを導入する際に、失敗する例も見受けられます。ここでは、よくある失敗パターンを紹介します。事前に「つまずきやすい箇所」を把握し、対策を講じることで、導入の成功率を高められます。
評価者の知識不足でバイアスが発生する

360度評価システムを導入すれば、客観的な評価が実現するとは限りません。システムを導入しても、評価者への教育を怠ると、評価にバイアスが生じる可能性があります。システムの使い方を理解したとしても、評価基準・目的・方法を理解していなければ、個人的な解釈で評価を行ってしまうからです。たとえば「寛大化傾向」として全員を甘めに評価したり、「厳格化傾向」として厳しく評価することが挙げられます。
また、一部の行動や印象に引きずられ、ほかの側面を適切に評価できないこともあります。たとえば、普段から明るい社員に、その印象でコミュニケーション能力を高く評価することもあるでしょう。実際には、意見を聞く姿勢に問題があるかもしれません。評価者の知識不足でバイアスが発生しないよう、評価者研修を実施するなどの対策が必要です。
フォローアップが欠如している
360度評価を実施した後、評価結果を返却するだけで終わるケースは、システム導入の効果を損なう典型的な失敗パターンです。貴重な評価データも、その後の適切なフォローアップがなければ、具体的な行動変容にはつながらないでしょう。
とくに、自己評価と他者評価との間に大きなギャップが見られる場合、その理由や背景にある認識のずれ、具体的な改善方法についての対話が不可欠です。
失敗を防ぐには、評価結果の返却後に「1on1ミーティング」を必須のプロセスとすることが重要です。また上司に対して、建設的なフィードバックを行うためのトレーニングを提供する必要があります。1on1ミーティングをより効率的に、かつ効果的にすすめたい場合には、「1プロ」のような1on1に特化した専門サービスの活用も有効です。
360度評価システム導入の成功事例
ここでは、360度評価システムを導入し、成功した事例を紹介します。成功パターンを知ることで、システム選びをスムーズにすすめやすくなります。
組織活性化を目指した製造業A社

製造業A社では、従業員の意欲向上と部門間の連携強化を目的に、360度評価システムを導入しました。導入にあたり、全従業員に対し、評価の目的や意義を説明する説明会を実施。
システム選定では、匿名性が高く、自由記述形式のコメントを重視できる点を重視。また「コミュニケーション能力が高い」といった抽象的で解釈がわかれる評価項目を、「問い合わせを24時間以内に返信する」「会議では全員に発言の機会を設ける」といった、具体的な評価項目に落とし込みました。これにより、評価バイアスを排除し、日々の業務行動に基づいた客観的な評価が実現。具体的な行動が評価されることで、貢献度が明確になり、日々の業務へのモチベーション向上につながりました。また、部門をまたいでの評価やコメントを通じて、相互理解も深まります。その結果、部門間の協力意識が醸成され、連携強化にもつながりました。
人材育成・定着率向上を実現したIT企業B社
IT企業B社では、若手社員の育成と早期離職の抑制を目的に、360度評価システムを導入しました。評価項目には、技術スキルだけでなく、チームワークやコミュニケーション能力といった定性的な要素も反映。また評価結果について、1on1ミーティングで詳細なフィードバックを行いました。特に、自己評価と他者評価のギャップが大きい項目については、具体的な改善策を一緒に検討することで、若手社員の成長を具体的にサポートしました。
定期的な360度評価を通じて、成長の過程を可視化でき、達成感とモチベーション向上に貢献。結果として、社員の定着率も高まっています。
リーダーシップ開発をすすめるサービス業C社
サービス業C社では、次世代リーダーの育成とリーダーシップ能力の向上を目的に、360度評価システムを導入しました。評価対象は管理職層に限定し、リーダーシップに関する独自の評価項目を設定。部下からの評価だけでなく、同僚や上層部からの評価も加えることで、複数視点から見た「リーダーシップの強み」と「課題」が明確になりました。
評価結果は、個別のリーダーシップ研修カリキュラム設計に活用。研修後も定期的に360度評価を実施し、成長度合いを比較しつつ、継続的に能力支援を行っています。評価結果をオープンにすることで、管理職層全体のリーダーシップ意識の向上にもつながっています。
360度評価システムの導入でよくある質問
つづいて、360度評価システムの導入を検討する場合に、よくある質問とその回答をご紹介します。導入にあたっての疑問や、不安の解消にお役立てください。
Q1: 中小企業でも360度評価は効果がありますか?
A: むしろ中小企業の方が、変化を早く実感できる傾向にあります。人数が少ないからこそ、一人ひとりの行動が組織全体に与える影響が大きいからです。複数名からの具体的で率直なフィードバックは、「自己の行い」と「周囲への影響」をダイレクトに結びつけやすくなります。
Q2: 導入にあたって最低限必要な準備は何ですか?
A: 少なくとも、「導入の目的」や「評価項目」を検討することが大切です。加えて、360度評価の制度そのものを整備することも忘れてはいけません。評価項目の設定に不安がある場合や、社内に専門的な知識を持つ人材が不足する場合には、コンサルティングサービスも行うベンダーを選ぶのもよいでしょう。
Q3: 匿名性は確保されますか?
A: 多くのシステムでは、匿名性を確保する機能が実装されています。基本的に、個別の回答者が特定されないよう配慮されているため、システム上から情報が漏れることはありません。
ただし、少人数組織の場合、評価者の人数が限られるため、完全な匿名性の確保が難しい場合もあります。そのようなケースでは、評価項目の粒度を細かくしすぎない、コメントの表現に配慮を促すなど、運用面での工夫も検討するとよいでしょう。
Q4: 360度評価を人事評価に直結させるべきですか?
A: 導入初期は人事評価(昇進・昇格・報酬)から切り離し、育成目的での運用から始めることをおすすめします。評価結果が処遇に直結すると、本音での評価を避ける傾向にあるからです。信頼性のあるデータが蓄積され、組織に評価文化が定着した後(通常1〜2年後)、段階的に人事評価への活用を検討するのが理想です。
Q5: 評価の頻度はどれくらいが適切ですか?
A: 組織の状況に応じて、調整するとよいでしょう。年1回の場合は、人事評価と連動させやすく、評価者の負担も抑えられるメリットがあります。一方、半年に1回やプロジェクト終了時など、より高頻度で実施すれば、タイムリーなフィードバックにつながります。
昨今では、サイクルを短くし、項目を絞った「ライト版」の評価を実施する企業も増えています。
360度評価システムを活用し、組織の成長を加速させよう
360度評価システムは、複数の関係者が評価するため、公平性の高い評価を実現できます。従業員の納得度を高め、定着率やモチベーションをアップさせるなど、組織の活性化も後押しします。
また導入にあたっては、自社の目的を明確にし、予算・運用体制・必要な機能などを検討することが重要です。当記事で紹介した選び方のポイント・成功事例・よくある質問などを参考に、最適なシステムを選んでください。
サポート体制を重視し、操作性の高いシステムを希望する場合には、『評価ポイント』がおすすめです。詳細を知りたい場合には、お気軽に資料を無料ダウンロードしてください。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル