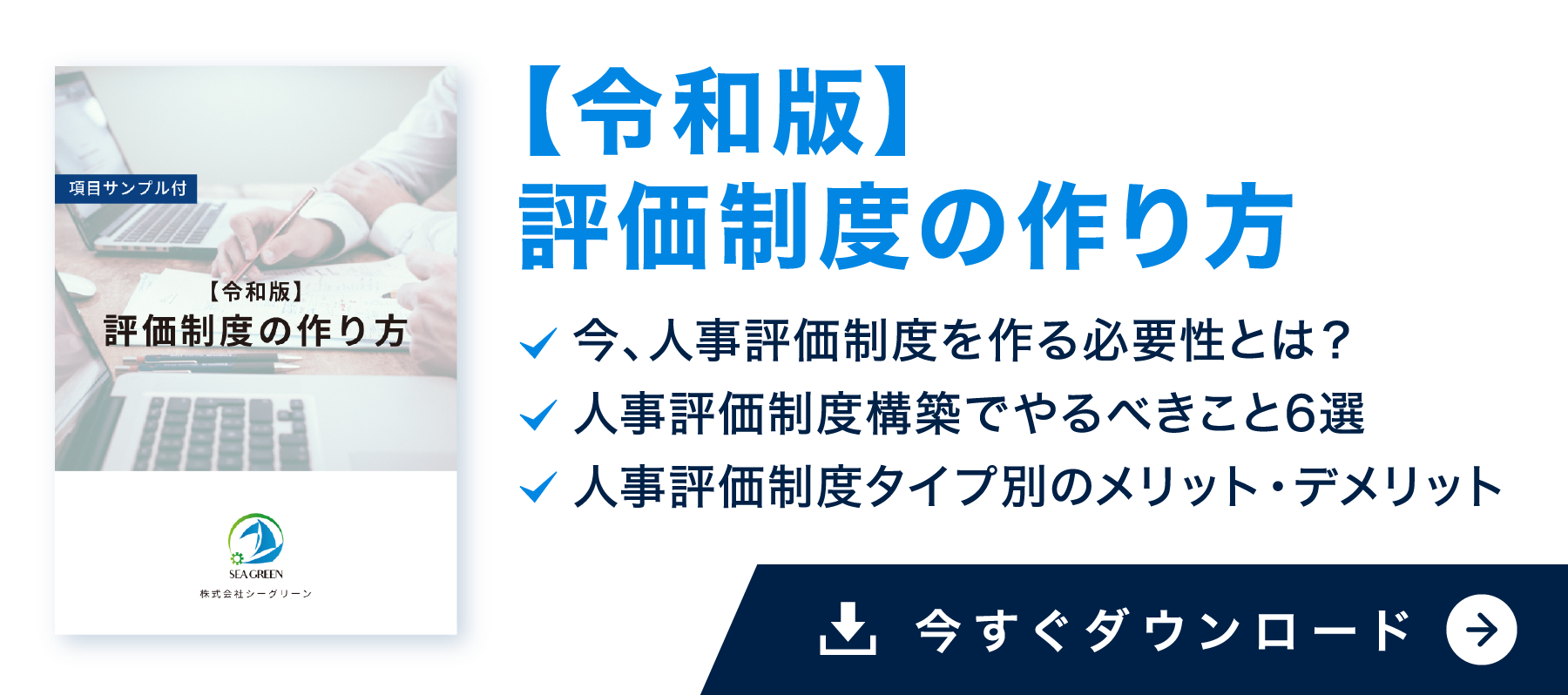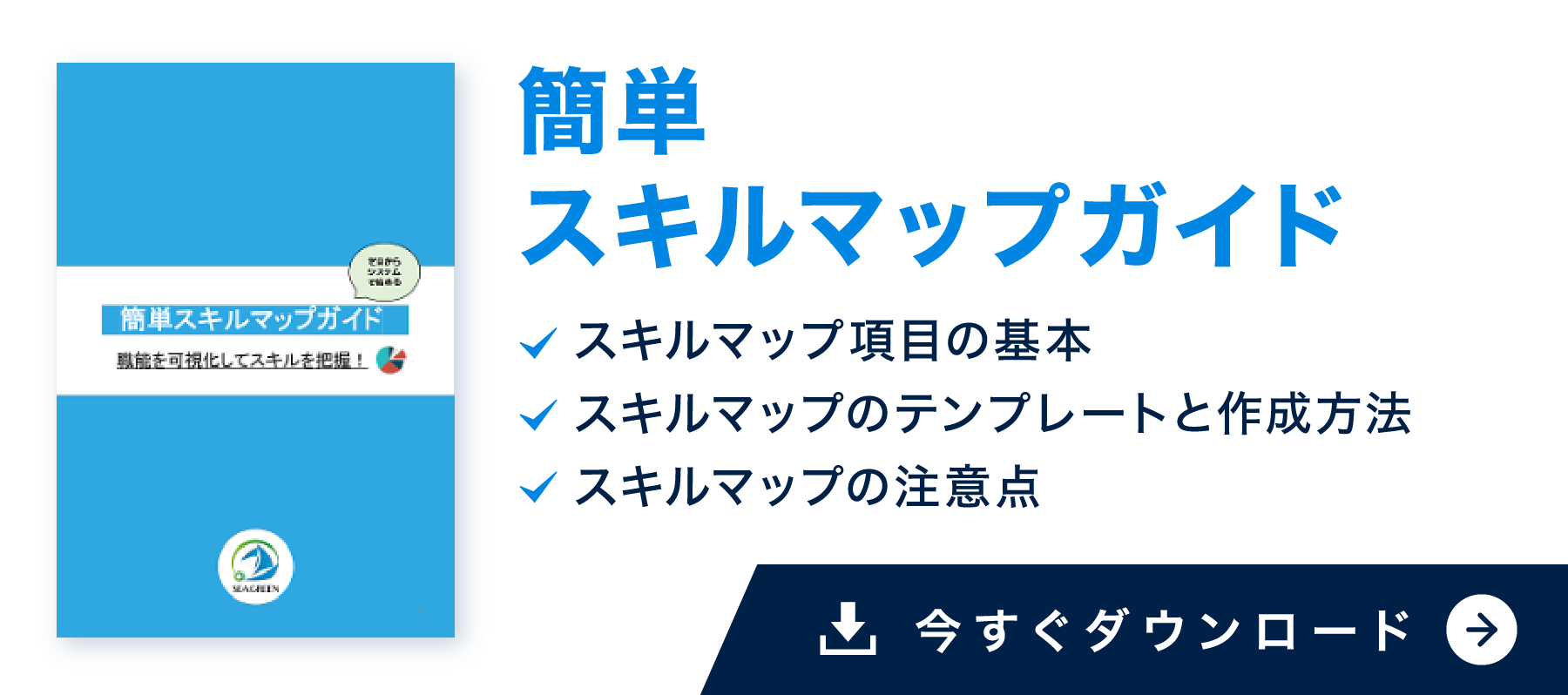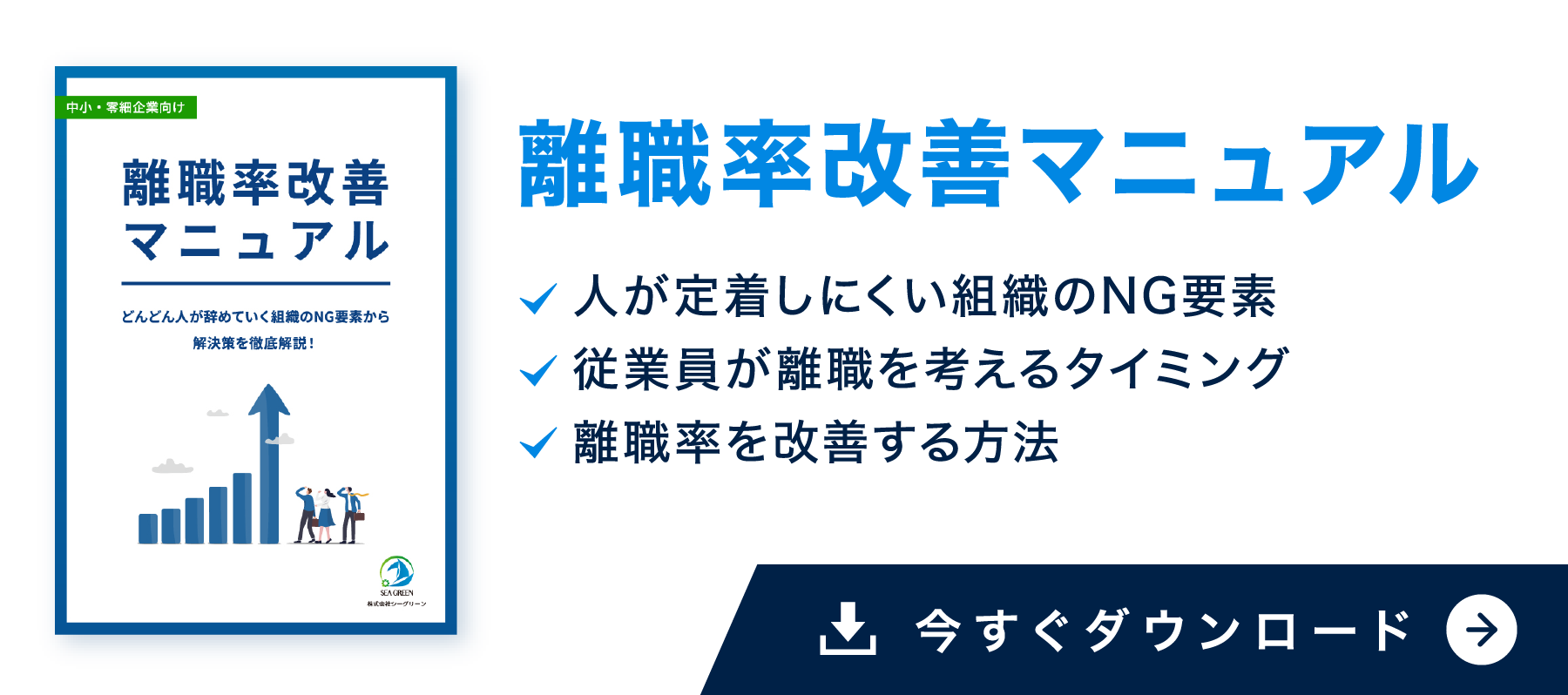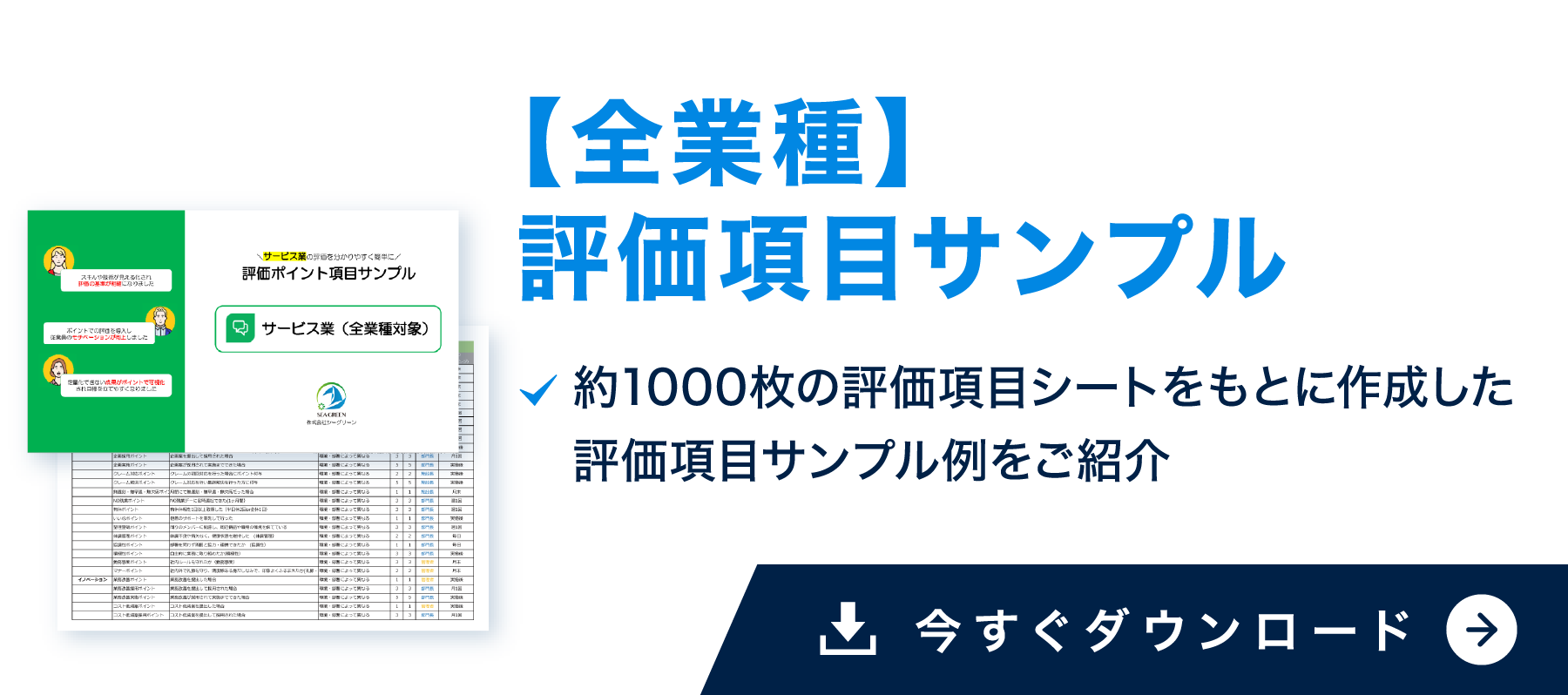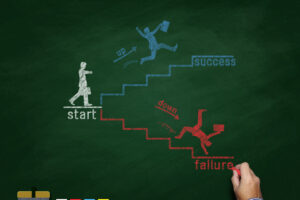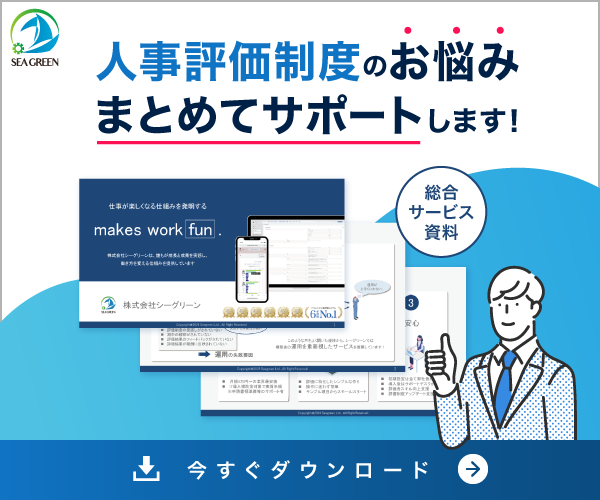中小企業では、社員一人ひとりの頑張りが、会社の成長に大きく影響します。だからこそ、「社員の頑張りがきちんと評価されているだろうか?」と、常に気にする経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。少ない人数で評価業務に手が回らず、公平な評価制度の構築に悩む人事担当者もいるでしょう。
当記事では、適切な評価に悩む中小企業が人事評価システムを導入し、課題を解決するための具体的なコツを紹介します。人事評価システムの選び方も解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
中小企業向け人事評価システムとは?

中小企業向けの人事評価システムは、人的リソースや予算の限られた中小企業が、効率的に人材評価を行えるように開発されています。導入コストを抑えながらも必要十分な機能を備え、運用負担を軽減するよう設計されている点が特徴です。
目標設定・評価シート作成・評価の実施・集計、フィードバックといった、一連のプロセスを搭載することも多いでしょう。また中小企業向けの人事評価システムは、大企業向けの複雑なシステムとは異なり、中小企業の規模やスピード感に合ったシンプルな運用が可能です。導入後の混乱を最小限に抑え、スムーズな評価ができるような設計にもなっています。
中小企業における人事評価業務の課題
中小企業では、人事評価業務を行う際に、特有の課題が見受けられます。課題が、人材の定着や育成を妨げることも多いでしょう。主な内容は、以下の通りです。
評価業務が属人化する
中小企業では、人事専任の担当者がいないケースや、存在してもごく限られた人数ということも多いでしょう。そのため、経営者や一部の管理職が、本来の業務に加えて評価業務を兼任することも少なくありません。結果として、評価業務に十分な時間を割けず、評価制度を整備する余裕がないことも多く見うけられます。
また、評価に関する専門知識や経験が不足しがちなため、評価結果が経営者や上司の主観に左右されることがあります。従業員は評価の透明性や公平性に不満を感じやすく、モチベーション低下や不信感につながる可能性があります。
評価基準が曖昧で客観性が不足する
明確な評価基準が曖昧な場合、評価者は、何に基づいて判断すればよいかがわかりません。そのため、評価は必然的に曖昧になり、「なぜこの評価結果になったのか」を論理的に説明することが困難になります。従業員も、「自分の何が評価され、何が問題なのか」を理解できず、キャリアの方向性や成長目標を見出せないでしょう。
明確で体系的な基準がないことは、評価プロセス全体の信頼性を損ない、従業員の納得感を低下させます。モチベーションもダウンしがちであり、最終的には離職率の上昇につながります。課題解決には、評価基準を明確に定義し、一貫して適用できる方法を考えることが大切です。
紙やExcelベースの運用による管理の煩雑さ
中小企業では、「コストの問題」や「従来の方法に慣れている」といった理由から、紙やExcelで評価をつづけるケースも少なくありません。しかし、紙やExcelといったアナログな方法では、評価シートの配布・回収・集計・管理などに、多くの手間と時間がかかってしまいます。
また、データの入力ミスや紛失のリスクも考えられます。とくに複数拠点や他部門にわたる場合、提出遅延が見受けられることもあるでしょう。そのため、アナログでの評価は、効率的な方法とはいえないでしょう。煩雑な評価業務は人事担当者の負担を増大させ、本来注力すべき戦略的な業務の時間を奪ってしまいます。
フィードバックの機会が不足する
評価結果のフィードバックは、成長を促し、モチベーションを維持するために不可欠です。しかし、中小企業の現場では、さまざまな理由からフィードバックできていないことも多いでしょう。
なぜなら、管理職や人事担当者は、本業の傍らで評価業務を行うことが多いからです。フィードバックの時間は、後回しになりがちです。また、管理職自身が適切なフィードバックを受けた経験がなく、「何をどう伝えればよいかがわからない」ことも理由として挙げられます。しかし、このままフィードバックの機会を設けないと、成長機会の損失や会社への不満につながります。
評価・報酬・育成の連携が不足する
人事評価は、「評価→報酬・育成→成長→次の評価」という一連のサイクルとして機能することで、初めて効果を発揮します。しかし、中小企業の現場では、連携が不十分なケースも多いでしょう。
たとえば、高評価を得た社員の給与が据え置かれると、「頑張っても報われない」という不満が生まれます。また評価で「プレゼンテーションスキルの課題」を指摘されても、具体的な育成計画や研修機会が提供されなければ、課題の解決につながりません。さらに、前年の評価結果や課題が、次年度の目標設定や評価に活かされないケースもあり、「毎年同じことを指摘されるだけ」という停滞感を従業員に与えてしまいます。
中小企業における人事評価システムの重要性
中小企業にとっても、人事評価制度を設けることは大切です。ここでは、アナログ管理ではなく、人事評価システムを活用することの重要性をについて解説します。
取り巻く環境が変化している

労働人口の減少や働き方の多様化によって、ビジネスシーンは、刻一刻と変化しています。環境の変化は、中小企業にとって「従来のやり方では通用しない」ことを意味するでしょう。変化するなかでも成長をつづけるには、限られた人材を有効活用し、個々の能力を最大化する必要があります。
人事評価システムは、個々の「目標達成度」「スキル」「組織への貢献度」などを、明確な評価基準に基づいて可視化することが可能です。すると、従業員の能力も適切に把握できるようになります。評価データをベースとし、各自に合わせた育成計画やキャリアパスを検討すれば、個々の能力を最大化することにつながります。
人材獲得の競争が激化している
少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少に拍車がかかっています。また働き方の多様化によって、企業に属さない人も増えています。そのため、多くの企業は人材の獲得に苦戦していることも事実です。中小企業の状況は、大企業よりも顕著です。
厳しい人材獲得競争を勝ち抜き、優秀な人材を定着させるには、公正な評価制度を構築し魅力的な職場環境を提供する必要があります。人事評価システムを導入すれば、システム上で評価基準や目標が共有され、評価プロセスも可視化されます。従業員目線でも、どのように評価され、どういった部分で貢献しているかを理解しやすいでしょう。
働き方が多様化している
昨今では、リモートワークや時短勤務など、ビジネスパーソンの働き方が多様化しています。多様なワークスタイルが浸透する現代において、従来の一律的な管理方法では、従業員の貢献度を正確に把握することはむずかしいでしょう。多様な働き方をする従業員の成果を公平に評価し、一人ひとりの能力を最大限に活かすには、柔軟な人事評価システムの導入が不可欠だといえます。
人事評価制度を整えることは、もちろん重要です。さらに、システムを導入することで、多様な働き方の変化に合わせて、評価項目やプロセスを迅速かつ柔軟に調整できるでしょう。
人事評価の効率化が求められる
中小企業では、評価業務を行う専任の人がいないケースも多いでしょう。存在する場合にも、他の業務と兼務していることが多く、人事評価業務は大きな負担となる傾向にあります。状況を改善し、本来の業務に注力すべく、人事評価の効率化は課題です。
人事評価システムを導入すれば、評価シートの作成・配布・回収、評価結果の集計、フィードバックの記録などの煩雑な作業を効率化できます。また、システム化されていることから、評価データや関連情報を一元管理できるため、複数の場所に散在する情報を探す手間が省けます。手入力によるミスも削減され、集計作業なども自動化されるため、大幅な時間短縮につながるでしょう。
モチベーションを左右する
評価結果は、従業員のモチベーションに影響を与えます。評価が不公平であったり、基準が曖昧であったりすれば、従業員の不満は募ります。その結果、エンゲージメントの低下や、離職といった自体につながりかねません。
負の連鎖を断ち切るには、公平で透明性の高い評価制度を構築し、制度を効果的に運用するための人事評価システムの活用が不可欠です。
人事評価システムは、客観的なデータに基づいて評価を行うため、評価の透明性を高めます。従業員も、自身の貢献を客観的に理解でき、正当に評価されている実感にもつながります。自身の貢献が明確になることで、次の目標への意欲が高まり、モチベーション向上が期待できるでしょう。
中小企業が人事評価システムを導入するメリット
中小企業が人事評価システムを導入する場合、多くのメリットを享受できます。主なメリットは、以下の通りです。
限られたリソースでも評価できる

中小企業では、人事専任担当者が不在であるケースも少なくありません。その場合、経営者や管理職など、ほかの業務を行う人が並行して評価業務を担当するケースが多いでしょう。また昨今では、多くの中小企業が「人手不足」や「採用難」といった問題を抱えています。限られた人員で効率的に組織を運営していくには、煩雑な評価業務に多くの時間を割くことは避けたいのが実情です。
人事評価システムは、評価に関する業務を自動化できるため、非効率な管理からの脱却につながります。評価業務が効率的に行えれば、評価業務に関わる経営者や管理職などの時間的負担を軽減できます。その分、本来の業務や経営戦略に集中できるでしょう。
属人化を防止できる
中小企業における人事評価は、「評価制度自体の不備」「評価者の経験・スキル不足」「コミュニケーション不足」などの要因によって、属人的になりがちです。属人的な評価は、評価者の好き嫌いでの不公平な判断や、貢献が正しく評価されないといった理由で、従業員の不満や不信感を招くことが多いでしょう。不満や不信感は、モチベーション低下や離職につながりかねません。
人事評価システムを導入すれば、評価項目と基準を全社で共有できることから、透明性が確保できます。また評価者も、システムに沿って評価を行うため、個人の主観や経験に左右されにくくなるでしょう。評価者が異なっても、評価結果のばらつきを防止できます。
少数精鋭の人材育成につながる
中小企業では、一般的に人員規模が限られます。各従業員が担う業務範囲も広く、各自の能力や貢献度が企業の業績に直接的に影響しがちです。そのため、中小企業では、限られた人員で多様な業務をこなす必要があります。
人事評価システムを活用すると、従業員のスキル・強みや弱み・目標を一元的に管理できるため、各自の特徴や状況がクリアになるでしょう。すると、各自に合わせた育成が実現します。たとえば、評価データから「プレゼンテーションスキルに課題がある」と特定された従業員には、個別にレクチャーを行えます。また、システム上で過去の評価結果を比較分析できるため、個々の成長度合いも都度チェックできます。
中小企業が人事評価システムを導入するデメリット
中小企業が人事評価システムを導入する場合、多くのメリットがあるとわかりました。一方で、システム導入にはデメリットもあります。主な内容は、以下の通りです。
コストがかかる

人事評価システムを導入する際には、初期費用や、システムの種類によってはサーバーなどの設備投資が必要となる場合があります。また、月額または年間の利用料、運用・保守にかかる費用も考慮しなければなりません。とくにオンプレミス型は、自社でインフラを構築・維持する必要があるため、長期的な視点でのコストを比較することが重要です。
近年主流となっているクラウド型は、初期費用を抑えやすく、必要な機能や利用人数に応じた柔軟な料金体系が多いです。そのため、中小企業にとって、導入しやすい選択肢だといえるでしょう。いずれのタイプを選ぶにしても、無料トライアル期間を積極的に活用したうえで、実際の使い勝手や費用対効果を見極めることが大切です。
開発・運用の負担がある
人事評価システムの導入では、「自社の状況に合うシステム設定」「従業員データの移行」「新制度に合わせた運用ルールの策定」など、多くの準備作業が必要になります。IT専任の担当者がいない中小企業では、開発や運用の作業が、担当者の大きな負担となる可能性が高いでしょう。
そのため、システム選定の際には、導入時の設定支援だけでなく、運用開始後のサポート体制も充実しているベンダーを選ぶことが大切です。データ移行の代行や、運用ルールの策定に関するコンサルティング、トラブル発生時の迅速な対応など、手厚いサポートがあれば、システムに不慣れな企業でも安心して導入・運用を進められるでしょう。
システムの定着に時間がかかる
人事評価システムは、導入しただけですぐに効果を発揮するものではありません。従業員にとって新しいツールであり、評価制度や考え方そのものが変わる場合もあるため、浸透には一定の時間を要します。システム操作の説明をはじめ、新制度の目的や意義を伝え、理解と納得を得るための時間を設けることも重要です。また、人事評価システムの形骸化を防ぐために、ルールの明確化や徹底も求められます。
導入初期は混乱も予想されるため、問い合わせ窓口の設置やフォローアップ研修の実施など、サポート体制を整えることも大切です。焦らず根気強く、従業員と共にシステムを活用していく姿勢で過ごすとよいでしょう。
中小企業における人事評価システムの比較ポイント5選
人事評価システムを選ぶ際には、ポイントを踏まえて比較する必要があります。ここでは、中小企業が人事評価システムを比較する際に、チェックすべきポイントについて解説します。
企業規模に合う

人事評価システムを選ぶには、自社の規模感に合ったものを選ぶことが重要です。たとえば、大企業が使っているような、大人数に適したシステムを選んでしまうと、機能過多でコストが高くなる可能性があります。
また、中小企業向けの人事評価システムを選ぶ場合にも、従業員数・評価の階層・部門数などに適したシステムを選ぶことが必要です。将来的に規模が大きくなり、組織構造が複雑化する可能性も考慮する必要があるでしょう。そのためには、ある程度の拡張性を持つシステムを選ぶことが大切です。現時点での最適解だけでなく、将来的な成長を見据えた選択が、長期的な視点ではコスト効率を高めることになります。
搭載した機能のバランス
人事評価システムに求める機能は、企業によって異なります。業種・事業規模・組織構造・企業文化はもちろんのこと、人事評価制度の目的も異なるからです。目標管理を重視する企業もあれば、コンピテンシー評価を主体とする企業もあります。たとえば、従業員の成長支援に重きを置く企業では、フィードバック機能や育成計画との連携機能が不可欠となるでしょう。一方、評価業務の効率化が最優先であれば、シンプルな評価シート作成・集計機能が中心となるかもしれません。
中小企業では、とくにリソースも限られているため、具体的な課題や目的に合致した機能を見極めることが重要です。複雑すぎる多機能なシステムは、使いこなせないだけでなく、コストもかさむ可能性があります。
コストパフォーマンスと費用体系
中小企業では、大企業と比較すると、自己資本や資金調達の選択肢が限られています。一つ一つの投資が経営に与える影響が大きく、無駄なコストは経営を圧迫しかねません。そのため、限られた予算内で最大の効果を得ることが求められます。人事評価システム導入においても、費用対効果を慎重に見極めることが不可欠です。
初期費用・月額費用・カスタマイズ費・保守費用など、導入から運用にかかるトータルコストを把握したうえで、自社の予算規模に見合ったシステムを選定することが重要です。また、従業員数の増減や機能拡張に応じて柔軟に対応できる料金体系であるか、追加料金がなるべく発生しない明確な料金体系であるかもチェックしましょう。
自社の評価制度との互換性
すでに運用している人事評価制度がある場合、既存の評価項目・評価基準・評価プロセスなどが、導入を検討しているシステムに適合できるかをチェックすることは重要です。既存の評価制度を大きく変更してしまうと、従業員が制度の変更に戸惑い、混乱を招く可能性があります。システム導入の際には、既存のよい点を活かしつつ、効率化や課題解決に必要な機能をシステムで補完するという視点が重要になります。
一方、これから新たに人事評価制度を構築する場合には、システム導入と制度設計を同時に進められるサポート体制の有無がポイントです。制度設計のノウハウを持つベンダーの支援を受けることで、自社の経営戦略や企業文化に合致した、実効性の高い評価制度を構築できます。
操作のしやすさ
中小企業では、大企業と比較すると、「IT専門の担当者がいない」「IT担当者が別業務も兼任する」といったケースが多いでしょう。従業員のITスキルも、ばらつきが生じる傾向にあります。そのため、人事評価システムには、誰もが直感的に操作できる使いやすさが必要です。また複雑な操作が必要なシステムは、導入後の混乱や利用率の低下を招きかねません。
人事評価システムを選ぶ際には、画面構成が見やすく、操作手順がシンプルであることが重要です。実際にデモ画面などでチェックし、操作のしやすさを確認するとよいでしょう。ITに詳しくない社員でも迷わず操作できるようなシステムであれば、導入時のトレーニングにかかる時間や労力も最小限で済みます。
中小企業が人事評価システム導入で成功した事例紹介
つづいて、中小企業が人事評価システムを導入し、成功した3つの事例を紹介します。
事例1:従業員数30名の製造業:評価の公平性向上でモチベーションアップ

製造業を営むA社は、従業員数が30名ほどの中小企業です。上司の判断による「主観が入りがちな評価」が行われており、従業員の間で評価の透明性や公平性に対する不満が蓄積していました。マイナスな状況を打破するために、クラウド型人事評価システムを導入しました。
すると、これまで曖昧だった評価項目と評価基準がシステムで一元化されたため、上司の主観が混じらず客観的な評価ができるようになりました。また全従業員に公開したことで、評価の軸も可視化され、評価に対する透明度が高くなりました。
従業員からも、「自身の評価理由や改善点がわかった」「評価結果に透明性が出たので納得できる」といった声が聞かれるように。その結果、評価に対する不満は減少し、意欲の高い社員が増えました。事実、離職率の低下にもつながっています。また、これまで手作業で行っていた評価シートの作成や集計作業がシステム化されたことで、管理職の評価業務にかかる時間的な負担も大幅に減りました。
事例2:従業員50名のIT企業:目標達成率向上で業績アップ
従業員50名ほどのIT企業B社では、個々の業務目標が不明確で、設定されたとしても進捗状況を組織で共有・管理する仕組みが整っていませんでした。従業員の目標達成への意識も低く、組織全体のパフォーマンス向上も頭打ちとなっていました。この状況を改善するため、人事評価システムを導入しました。
システム上では、各従業員が設定した目標と進捗状況がリアルタイムでわかるようになりました。その結果、軌道修正も容易になりました。また、評価結果を昇給や賞与といった待遇に明確に連動させたので、従業員の目標達成意欲を高めることに成功。さらに、評価結果に基づき、個々に必要な研修制度を受講させたため、従業員の成長を後押しすることにもつながりました。結果として、組織全体の能力向上と業績アップに寄与しました。システム導入による目標管理と評価の連動が、従業員の意欲と組織の成果を同時に高めた「成功事例」といえるでしょう。
事例3:従業員20名の飲食店:人材育成と定着率向上で組織力アップ
従業員20名の飲食店Cでは、先輩スタッフによるOJTが主な育成方法でした。そのため、個々のスキルや習得度が曖昧で、体系的な人材育成ができていませんでした。また、離職率が高いという課題にも直面していました。そこで、中小企業に特化した人事評価システムを導入し、従業員一人ひとりのスキルを可視化し、適切に評価できるようにしました。
また、評価結果と個々の目標を連動させた「キャリアパス」を提示し、将来の成長イメージを描きやすい状態にもしました。すると、従業員は自身の評価項目を意識するようになり、「調理担当者はより食材を丁寧に扱う」「接客担当者は積極的に顧客に声をかける」などの変化が見られるようになりました。 その結果、飲食店の利用者からも「料理が美味しくなった」「スタッフの対応がよい」といった高評価がつくようになりました。また、評価結果を給与や昇進といった待遇に反映させ、頑張りが報われる仕組みを構築し、従業員の定着率を高めることに成功しました。
中小企業が人事評価システム導入をする基本ステップ
実際に人事評価システムを導入する際には、基本ステップに沿って進めることを推奨します。ここでは、主なステップについて解説します。
目的を明確にする

人事評価システム導入にあたり、軸となる「導入目的」の明確化は欠かせません。「何となく便利そうだから」といった曖昧な理由ではなく、「評価業務を効率化させ、人事担当者の負担を軽減する」「評価基準の透明性を高め、従業員のエンゲージメントを高める」など、具体的な目的を設定することが望ましいです。目的が明確になることで、システム選定の軸が定まり、必要な機能や費用対効果の高いシステムを見極めやすくなります。
また、導入後の効果測定をする際にも、設定した目的が達成されたかを判断する基準となるでしょう。目的を明確にする際には、関係部署や経営層と十分に協議し、全社的な合意形成を図ることが望ましいです。
評価制度の見直し・新規作成
人事評価システムは、評価制度を効率的に運用するためのツールです。そのため、システム化する評価制度そのものが、「企業文化や経営戦略に合致しているか」「時代の変化に対応できているか」などを検討する必要があります。
既存の評価制度がある場合には、「評価項目や基準は適切か」「従業員の納得を得られるか」といった点を見直し、必要に応じて改訂を行いましょう。評価制度がまだ存在しない場合には、システム導入と並行して、自社に最適な制度を設計する必要があります。設計する知見が不足する場合には、専門家のサポートも視野に入れるとよいでしょう。また近年では、人事評価システムを提供するベンダーのなかに、評価制度の設計や見直しに関するサービスを提供する企業も存在します。そのようなサービスを活用すれば、効率的かつ整合性の取れた人事評価体制を確立できるでしょう。
システム選定をする
導入目的を洗い出し、評価制度を整えたら、いよいよ具体的なシステム選定に入ります。多種多様な人事評価システムが存在するため、自社の課題・予算・必要な機能・従業員のITリテラシーレベルなどを総合的に考慮し、複数のシステムを比較することが重要です。各システムの資料請求やデモ画面の確認に加え、実際に導入している同業他社の事例などを参考にするとよいでしょう。
また、ベンダーのサポート体制やセキュリティ対策なども、長期的な運用を考えると重要な選定ポイントとなります。人事評価システムを選ぶときは、価格や機能面だけを比較するのではなく、費用対効果をしっかりと見極めることが大切です。
無料トライアルを利用する
気になるシステムをいくつか絞り込んだら、積極的に無料トライアルを利用するとよいでしょう。無料トライアルを利用することで、テキストやデモ画面だけではわからない、実際の使い勝手や操作性がわかります。また、自社の評価制度との適合性、必要な機能が本当に搭載されているか、そして従業員がストレスなく利用できるかなどを、本番運用を想定してチェックすることも大切です。
無料トライアルを利用する際には、一部の従業員にテスト運用してもらうのも有効な手段です。また、トライアル期間中にベンダーのサポート体制もチェックしておくことで、導入後の疑問やトラブル発生時の対応力を確認することもできるでしょう。
システム導入(データ移行・テスト運用)
無料トライアルを経て、正式に導入するシステムが決定したら、システム導入の段階に入ります。運用元の指示に従い、システムの設定、従業員データの移行、評価シートのカスタマイズなどを行います。また、導入時に既存の評価制度や人事データをシステムに適切に移行することが、その後のスムーズな運用に不可欠です。
導入作業と並行して、一部の部署や従業員を対象としたテスト運用も実施しましょう。テスト運用を通じて、実際の業務フローとの適合性、システムの安定性、操作性の問題点などを洗い出し、本運用前に必要な修正や改善を行えます。また、中小企業の場合、IT専門の担当者がいないことも多いため、ベンダーが提供する導入支援サービスの内容や範囲を事前に確認しておくことが重要です。
従業員への研修・本運用をする
システム導入とテスト運用が完了したら、全従業員を対象とした研修を実施しましょう。研修では、単にシステムの基本的な操作方法の説明だけでなく、「人事評価システムの導入目的」「新制度の背景や評価項目やプロセス」などを説明し、従業員から理解と納得を得ることが不可欠です。 従業員の疑問や不安を解消することで、システム導入への抵抗感を減らし、積極的な利用を促すことにつながります。
研修後に、本運用を開始します。その際にも、従業員からのフィードバックを収集することが大切です。システムの操作に関する疑問、評価制度の運用における課題などを定期的に見直し、改善を重ねていく姿勢が求められます。 システムは導入して終わりではなく、組織の変化や従業員の意見に合わせて柔軟に進化させていくことで、効果を最大限に発揮できます。
中小企業向けのヒョーカクラウドがおすすめ
中小企業には、人事評価システム「ヒョーカクラウド」がおすすめです。その理由は、以下の通りです。
少ない負担で導入・運用が可能
「ヒョーカクラウド」は、中小企業の限られたリソースでも無理なく導入・運用できるよう、直感的なインターフェースとシンプルな機能設計にこだわっています。ITに詳しくない人でも、特別な研修なく容易に操作できるため、導入時の学習コストや担当者の説明時間を削減できます。複雑な操作が不要なので、評価者も被評価者も、ストレスなく使えるでしょう。
透明性の高い評価でエンゲージメント向上
目標設定から評価シートの作成・配布・回収、評価・集計・フィードバックまで、人事評価の一連のプロセスをクラウド上で一元管理できます。これまで手作業で行っていた煩雑な業務も効率化でき、人事担当者の負担を軽減します。また、評価基準の明確化や進捗状況の可視化により、評価の透明性と公平性を高め、従業員のエンゲージメント向上にも貢献します。
低コストで充実したサポート
中小企業にとって、コストも気になるところです。「ヒョーカクラウド」は、評価に必要な機能を網羅しながら、リーズナブルな価格設定を実現しています。初期費用を抑え、月額の利用料も抑えられています。導入後のサポート体制も充実しており、操作方法に関する問い合わせはもちろん、評価制度の運用に関する相談にも随時対応いたします。
「ヒョーカクラウド」は、無料トライアルも用意しています。「まずは試してみたい」という人や「少し気になる」という場合にも、お気軽にお試しください。
人事評価システムを導入し、企業の成長につなげよう!
人事評価システムは、中小企業が抱える人事評価の課題を解決し、持続的な成長を実現するためのツールです。評価業務の効率化・評価の公平性向上・従業員のモチベーションアップ・人材育成の促進など、メリットは多岐にわたります。
本記事で解説したシステムの選び方のポイントや導入ステップを参考に、ぜひ自社に合った最適な人事評価システムを見つけてください。システムを効果的に活用することで、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の成長へとつなげていきましょう。「ヒョーカクラウド」では、無料トライアル制度を用意しているため、まずはお気軽にお試しください。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル