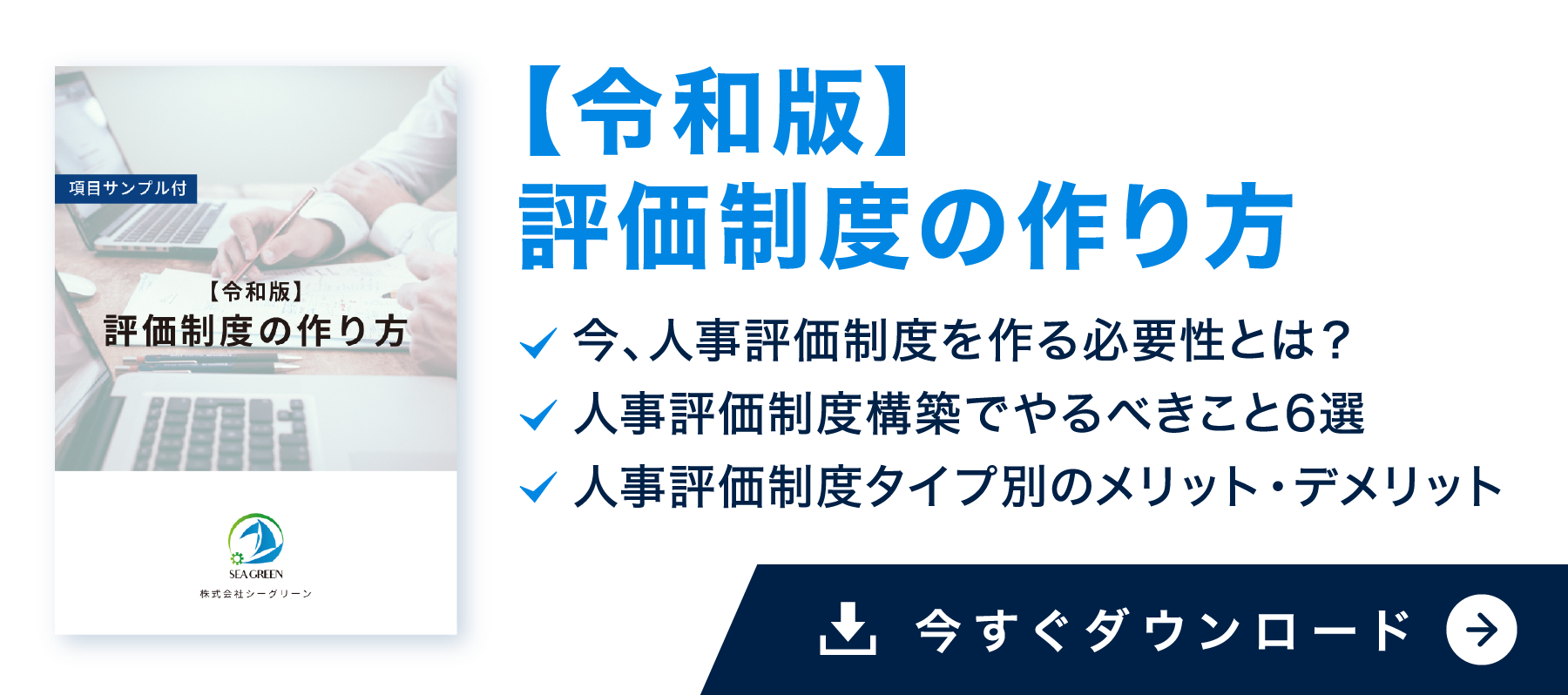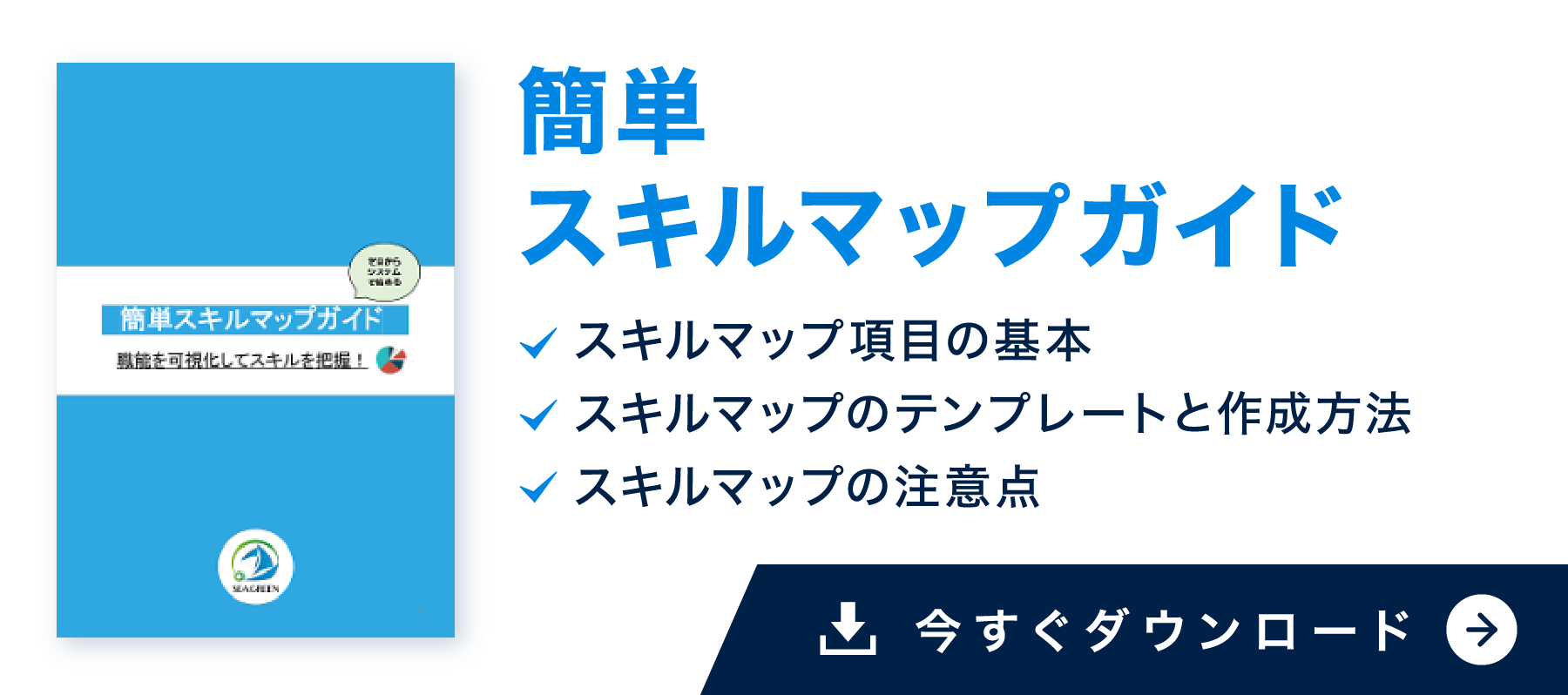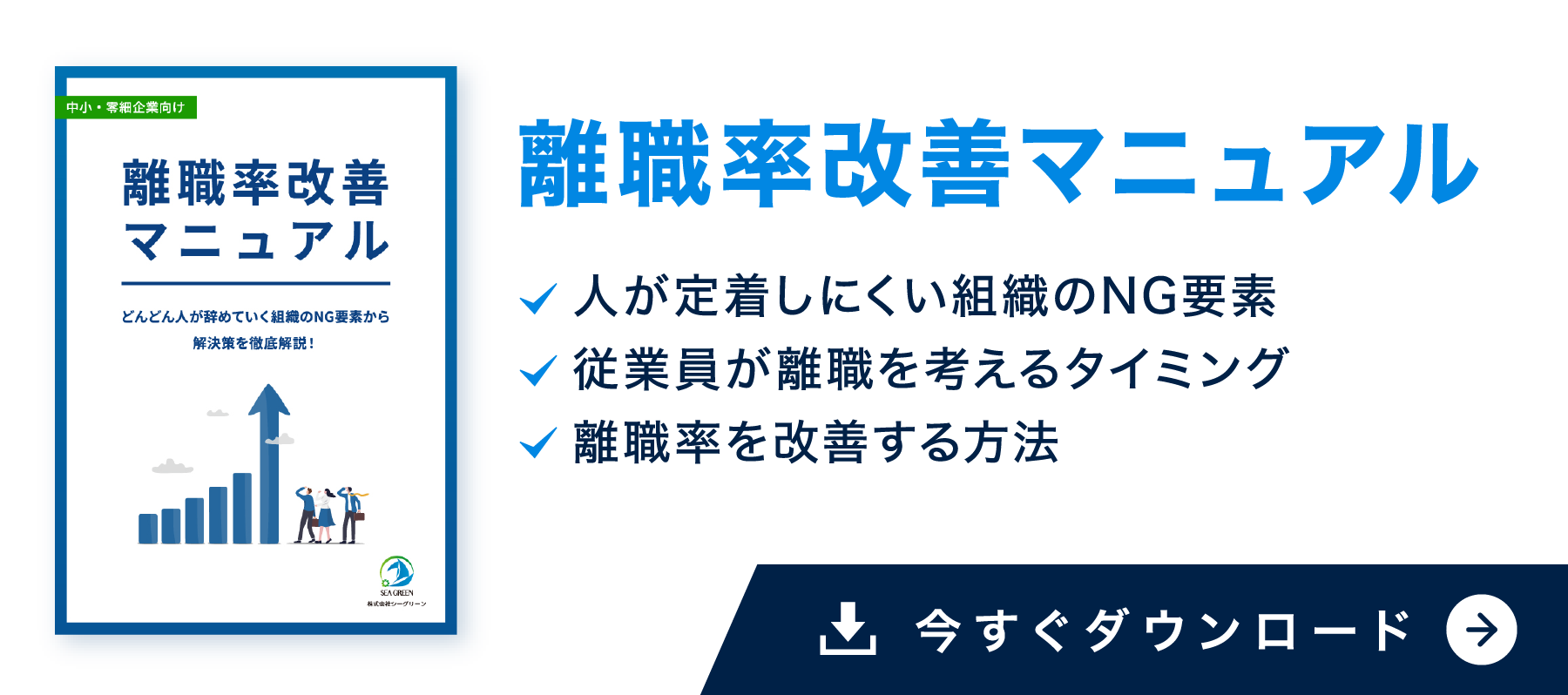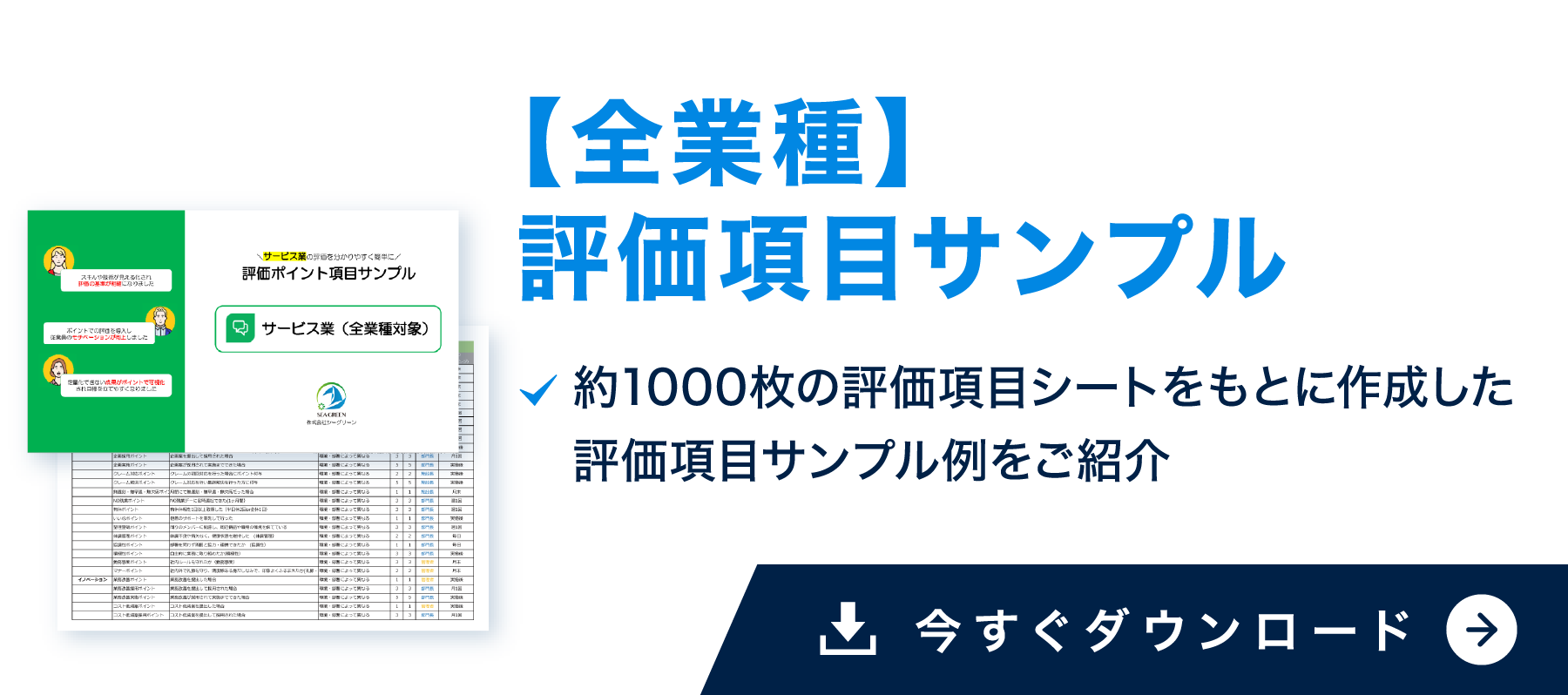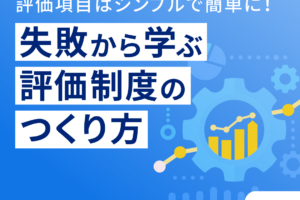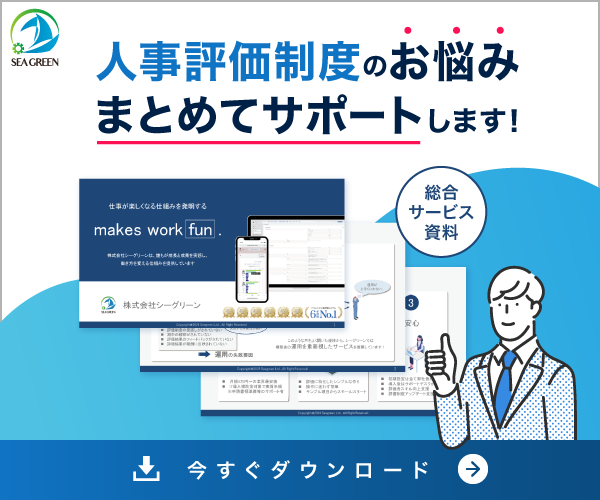部下を適切に育成したいと思うものの、「うまく育成できない」「育成方法がわからない」といった悩みを抱える上司も少なくありません。しかし、ポイントを押さえて適切に行動すれば、部下を成長させられます。
そこで当記事では、部下育成でよくある悩みや、育成で差がつく具体的な実践方法について紹介します。育成が得意な上司に見られる特徴や、階層別の育成ポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
部下育成でよくある5つの悩み
部下育成において、上司はさまざまな悩みを抱えています。ここでは、代表的な5つの悩みを紹介します。
コミュニケーションがうまくいかない

部下とのコミュニケーションが円滑でない場合、指示や期待が正確に伝わりません。すると、自分の役割ややるべき内容が理解できず、仕事の進行が遅れる可能性もあります。各自の悩みも把握しにくく、適切に対応できないこともあるでしょう。
コミュニケーションがうまくいかないと、部下との信頼関係も構築されにくく、モチベーションアップも難しくなります。
成果に対する評価が難しい
成果を適切に評価することは、容易ではないでしょう。適切な評価が難しい多くの理由として、評価基準の不明確さが挙げられます。評価基準が不明確だと、部下は「自分の成果がどのように評価されるか」がわからず、やる気を失ってしまいがちです。
上司自身も評価を行う際に迷いが生じ、適切にフィードバックできない可能性があります。
育成スキルに自信がない
育成スキルに自信がない上司は、部下の指導にためらいがちです。自信のなさは、「過去の経験」や「失敗から来る不安」が影響することも多いでしょう。何を教えれば良いのかわからず、結果として指導が進まなくなります。
育成知識や技能の欠如を感じ、部下との関係に距離が生じることも、信頼関係が築けない要因です。
時間がなく育成に取り組めない
業務に追われる上司には、育成に割く時間がないという悩みがあります。背景には、「日常業務の多忙」や「成果を求められるプレッシャー」が存在します。時間がないと、つい育成を後回しにしがちです。しかし、育成自体も業務の一部であることを忘れてはいけません。
多忙を理由に育成を怠ると、部下の成長機会を失いやすく、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を与える可能性があります。
育成できる上司と悩む上司の違い
部下の育成が得意な上司とそうでない上司には、いくつかの違いが存在します。ここでは、両者の違いについて、5つの観点から見ていきましょう。
明確な目標設定ができる

育成が得意な上司は、各自への明確な目標設定ができ、達成に向けて的確に導けます。具体的なゴールが設定されるため、従業員自身も進捗を確認しやすくなり、モチベーション維持につながります。
一方の育成で悩む上司は、「目標設定を怠る」や「曖昧なまま放置する」ケースもあり、各自の成長を促せません。目標が曖昧だと、何を目指すべきかがわからず、成長スピードが遅くなるでしょう。
適切なフィードバックができる
効果的なフィードバックは、従業員の強みを強化できると同時に、弱点の克服にもつながります。育成が上手な上司は、定期的にフィードバックを行う傾向にあり、適切な成長をサポートします。
育成に悩む上司は、フィードバックが不十分なケースも多いでしょう。フィードバックのタイミングを逃す人や、改善点を適切に伝えられない人も見受けられます。フィードバックが的確でないと、自分の改善点に気づくことが難しく、成長が遅れる可能性も否定できません。
部下の成長を見守る余裕がある
育成が得意な上司は、部下の成長を見守る余裕があり、彼らが失敗した際にも成長の機会として捉えることが特徴です。余裕がある上司のもとでは、従業員は安心して挑戦でき、失敗から学べるでしょう。同時に、部下の「自己成長に向かう意欲」も醸成できます。
対する育成に悩む上司は、自身の業務に追われてしまい、部下の成長に目を向ける余裕が持てないことも多いでしょう。余裕のない状況が続くと、各自の「成長の機会」を失ってしまいがちです。
コーチングスキルが高い
部下の育成が得意な上司は、コーチングスキルが高い人も多く、各自の能力を引き出せる人が多いでしょう。答えを与えるのではなく、自分自身で考えさせ、行動できるように導くことも特徴です。一連のプロセスを通じて、部下は自らの課題や目標を見つけ出し、解決能力を身につけられます。
育成に悩む上司は、コーチングスキルが不足することが多く、従業員の可能性を十分に引き出せません。指導も一方通行になりがちであり、成長を妨げられることが懸念されます。
時間の使い方が効率的
時間の使い方は、従業員を適切に育成するための重要ポイントです。限られた時間の中で効果的に育成を行うことで、成長を最大化できます。育成が得意な上司は、時間を意識的に管理し、育成に必要な時間をしっかりと確保します。適切な時間の使い方により、部下は適切なフィードバックを受けられるため、成長促進につながるでしょう。
一方で育成に悩む上司は、時間管理が不得意な傾向にあります。優先順位づけが苦手な人も多く、育成も後回しにしがちです。
階層別育成のポイント
部下の育成では、階層ごとに異なるアプローチが必要です。ここでは、新入社員・中堅社員・管理職候補の3つの階層に分けて、育成のポイントを解説します。
新入社員に向けた育成

新入社員には、基礎知識や業務の流れを理解させることが重要です。基礎がないと、業務の効率性や質が低下し、ミスが増える可能性もあります。業務の基本を把握することで、自信を持って業務に取り組むことや、スムーズなコミュニケーションにつながるでしょう。
「メンター制度」「研修プログラム」「定期的なフィードバック」などの機会を設け、実践を通じて、知識を習得する機会を増やすことが効果的です。
中堅社員に向けた育成
中堅社員は組織の中核を担う存在であり、将来的なリーダー候補です。そのため、「自分だけで業務を完結できる能力」について、習得させる必要があります。
育成では、責任のある業務を任せることが大切です。計画立案から遂行といった一連の流れを経験させ、自己成長を促進します。定期的なフィードバックやディスカッションの機会を設ければ、コミュニケーション能力やチームワークの強化にもつながるでしょう。
管理職候補に向けた育成
管理職は、「将来的な組織の方向性を決定する」という、重要な役割を果たします。そのため、管理職候補には、戦略的思考や人材育成能力を育てるプログラムが効果的です。
ケーススタディやロールプレイという手法を利用することで、実際のシナリオを体験し、問題解決や意思決定の力を鍛えられるでしょう。
- ケーススタディ…実際のビジネス事例を分析し、問題に対処する方法を考える手法
- ロールプレイ…参加者が特定の役割を演じ、設定されたシナリオを体験する方法
部下の育成を成功させる5つの具体的行動
部下の育成を成功させるには、具体的な行動が欠かせません。ここでは、5つの効果的な行動を紹介します。
定期的な1on1面談を実施する

定期的な「1on1面談」の実施は、部下の育成において重要であり、面談を通じて部下とのコミュニケーションを深められます。たとえば、部下の悩みや仕事上の目標を共有すれば、個々のニーズや課題を把握しやすくなるでしょう。1on1面談は一対一で実施するため、自分の意見を言いやすく、信頼関係の構築も期待できます。
また定期的に行うことで、状況の変化を見逃すことなく、迅速なサポートが可能です。1on1面談の質を向上させたい場合には、「1プロ(ワンプロ)」のような専門サービスの活用もおすすめです。
育成方法を学ぶ
上司自身が育成スキルを学ぶと、部下の育成成功に直結します。上司が育成手法や理論を学ぶことで、部下に対して、より効果的かつ適切なアプローチを実践できるでしょう。
たとえば、研修やセミナーに参加すれば、最新の育成理論や実践的なスキルを習得できます。またコーチングの技術を学べば、「部下の自己理解を深める」や「目標達成のサポート」につながります。上司自身が学ぶ姿勢を持つことで、部下に対しても成長の重要性を示せるでしょう。
部下をほめる文化をつくる
部下をほめる文化があると、心理的安全性や自己肯定感アップにつながり、モチベーション向上が期待できます。
ほめられることで、部下は自分の努力や成果が評価されたと感じるでしょう。「評価」は部下にとって励みとなり、やる気を引き出します。また自信を持った部下は、新たな挑戦に積極的になり、失敗への恐れが少なくなります。次のステップへの意欲も、生み出せるでしょう。
短時間でできる育成アクションを用意する
短時間でできる育成アクションを用意し、日常的に実践することが大切です。たとえば、1分間のフィードバックや感謝の言葉をかけるなど、短い時間でできる内容は意外と多いものです。小さなアクションであっても、積み重ねることで、部下は成長を実感しやすくなります。
また短時間であれば、忙しい中でも育成を行えるため、上司にも部下にも負担になりにくいでしょう。
明確な成長プランを設ける
部下の目標に合った「明確な成長プラン」を設けることは、着実な成長を促すために重要です。成長プランには、具体的な達成目標やスキル向上のステップが含まれます。
たとえば3か月ごとの目標を設定し、定期的に進捗を確認すれば、部下は自分の成長を実感しやすくなるでしょう。また、評価基準が明確な「ヒョーカクラウド」のようなシステムを活用すれば、達成度を具体的に測定できます。
具体的な育成アクションで部下の成長を加速させよう
部下を成長させるには、優れた上司の特徴を身につけることが大切です。階層別の育成ポイントを押さえ、具体的な育成行動を実践することで、部下の成長を加速させられるでしょう。
成長を継続的に追跡し、適切に評価したい場合には、人事評価システム「ヒョーカクラウド」がおすすめです。部下の目標達成度やフィードバックを一元管理でき、透明性のある評価が可能となります。
人事評価制度の構築から運用まで、全面的なサポートを希望する場合には、「人事評価構築パッケージ」の活用もご検討ください。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル